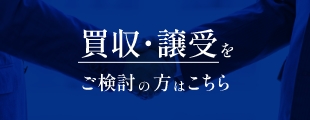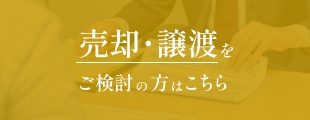平日9:00〜18:00

警備業界のM&A動向
業界別M&A
2024年における国内企業同士のM&A件数は、過去最多を更新しました。さまざまな業界でM&Aが進んでおり、警備業界でもM&Aを実施する企業が増えています。
警備会社のM&Aを検討している方は、まずは警備業界の現状を把握した上で今後の課題を理解することが重要です。
今回は、警備会社の概要と今後の課題、警備業界におけるM&A動向について詳しく解説します。立場別のメリットと主なM&A事例も紹介するため、ぜひ参考にしてください。
-
警備会社とは?警備業の定義と4つの分類
-
警備業界の現況|市場規模(業者数・売上高)の推移
-
警備業界の動向から見える今後の課題
-
警備業界におけるM&A動向
-
【警備会社】M&Aによる「譲渡側」のメリット
-
【警備会社】M&Aによる「譲受側」のメリット
-
警備業界における主なM&A事例2選
-
まとめ
基本合意まで無料
事業承継・譲渡売却はお気軽にご相談ください。
警備会社とは?警備業の定義と4つの分類

警備会社とは、依頼を受けた企業や個人の警備業務を行う事業です。警備業法では、他人の需要に応じて様々な警備にあたる業務を警備業務と定義しています。
(出典:e-Gov法令検索「警備業法」https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=347AC0000000117 )
日本は比較的治安が良く、警備業務の需要は低い傾向にありました。しかし、大規模イベント開催や高度成長期などの影響で安全や安全への意識が高まり、警備会社の市場は拡大しています。
警備会社の主な役割は、「施設警備」「雑踏・交通誘導警備」「運搬警備」「身辺警護」の4つです。複数の業務を実施する警備会社も少なくありません。
(出典:警察庁「令和5年における警備業の概況」https://www.npa.go.jp/publications/statistics/safetylife/r5keibigyougaikyou.pdf )
【第1号業務】施設警備
施設警備は、百貨店・企業・病院・空港などの警備を行います。第1号業務に分類され、国内の警備会社のうち約67%を占めます。
施設警備の主な業務内容は、下記の通りです。
- 巡回
- 出入管理
- 開閉館管理
- 防災センター業務
警備会社は、警備員の配置やモニター監視により対象施設の事故発生の警戒と防止にあたります。第1号業務の中で最も業者数が多いのは、施設の巡回と保安業務です。空港保安警備と機械警備を行う業者は少数です。
【第2号業務】雑踏・交通誘導警備
雑踏・交通誘導警備は、道路や駐車場における交通誘導により事故を防止します。第2号業務に分類され、国内の警備会社のうち約77%を占めます。
雑踏・交通誘導警備の主な業務内容は、下記の通りです。
- イベント会場や祭りの雑踏整理と交通誘導
- 部隊編成による警備
- 通行人や車両の誘導
人や車両の整理、交通誘導の他、イベントや祭りの参加者への情報提供や案内も重要な役割の1つと言えます。雑踏整理より交通誘導を実施する警備会社の方が多いことが特徴です。
【第3号業務】運搬警備
運搬警備は、主に現金や貴金属などの運搬中における盗難・紛失事故を防止します。第3号業務に分類され、国内の警備会社のうち約6%が実施しています。
運搬警備の主な業務内容は、下記の通りです。
- 対象物の安全な運搬
- 核燃料物質等危険物の安全な運搬
運搬警備の中には、現金や貴金属の運搬だけでなく原子力関連施設間での核燃料物質等危険物の運搬に携わる業者も含まれます。ただし、核燃料物質等危険物の運搬を実施する警備業者はごくわずかです。
【第4号業務】身辺警護
身辺警護は「ボディガード」とも呼ばれる分類で、対象者の身体に危害が及ばないように警護します。第4号業務に分類され、国内の警備会社のうち約6%が実施しています。
身辺警護の主な業務内容は、下記の通りです。
- 対象者の身辺を警戒
- 身体への危害の発生を防止
- GPSによる位置情報サービスの提供
- 緊急通報サービスによる現場急行
身辺警護の対象者は、著名人や要人だけでなく一般市民も含まれます。子ども・高齢者・女性などを対象としたサービスを提供する警備会社も多く見られます。
警備業界の現況|市場規模(業者数・売上高)の推移

警備業界の売上は、コロナ禍にやや減少しました。しかし、新型コロナウイルス感染症の沈静化によりイベント再開が増え、売上高は再び上昇しています。
ここからは、警備業界の現況を詳しく解説します。
警備会社・警備員数は増加傾向にある
警備業者数の推移は、下記の通りです。
| 2019年 | 9,908件 |
|---|---|
| 2020年 | 10,113件 |
| 2021年 | 10,359件 |
| 2022年 | 10,524件 |
| 2023年 | 10,674件 |
(出典:警察庁「令和5年における警備業の概況」https://www.npa.go.jp/publications/statistics/safetylife/r5keibigyougaikyou.pdf )
警備会社数は、右肩上がりの状況が続いています。高齢化や単身者世帯の増加、ATM設置数の増加などを受けて、今後も警備会社数は増加すると予想されています。
雇用別警備員数の推移は、下記の通りです。
| 常用警備員 | 臨時警備員 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 2019年 | 515,831人 | 54,896人 | 570,727人 |
| 2020年 | 534,584人 | 53,780人 | 588,364人 |
| 2021年 | 536,237人 | 53,701人 | 589,938人 |
| 2022年 | 532,322人 | 49,792人 | 582,114人 |
| 2023年 | 534,983人 | 49,885人 | 584,868人 |
(出典:警察庁「令和5年における警備業の概況」https://www.npa.go.jp/publications/statistics/safetylife/r5keibigyougaikyou.pdf )
全体の90%以上を常用警備員が占めています。常用警備員・臨時警備員どちらも女性の割合は約8%と少ないことが特徴です。 2023年と2019年で比較すると約14,000人以上増加しています。
売上高はほぼ同水準で推移している
警備会社数と警備員数は増加している一方で、売上高は2019年からほぼ同水準で推移しています。 警備会社の売上高の推移は、下記の通りです。
| 2019年 | 35,534億円 |
|---|---|
| 2020年 | 34,734億円 |
| 2021年 | 34,537億円 |
| 2022年 | 35,250億円 |
| 2023年 | 33,059億円 |
(出典:警察庁「令和5年における警備業の概況」https://www.npa.go.jp/publications/statistics/safetylife/r5keibigyougaikyou.pdf )
2022年から2021年は、新型コロナウイルス感染症の拡大により営業自粛をした施設も多く、売上高が一時的に減った警備会社が多く見られました。新型コロナウイルス感染症の沈静化により、2022年は警備会社への需要が回復したものの、2023年はまた売上高が大幅に下がっています。
警備業界では、「セコム」「綜合警備保障」の大手2社の売上高が突出しており、約9割のシェアを誇っています。M&Aの実施により、企業成長を続けていることが特徴です。
警備業界の動向から見える今後の課題

警備業界への需要がさらに高まることで、今後は業界内での競争がさらに激化する可能性があります。 競合他社との差別化や警備員の人材不足など、警備会社は様々な課題を抱えています。生き残りを目指すためにも、市場動向をチェックして必要な対策を講じることが大切です。
ここからは、警備業界の動向から見える今後の課題を2つ解説します。
競争の激化による価格引き下げの必要性
近年、セキュリティ意識が一層高まっており、今後も警備会社への需要増加が見込まれています。来月から開催予定の巨大イベント「大阪万博」も、警備業界の競争激化に繋がる要因の1つです。警備業界に参入する企業の増加に備えて、各警備会社では他者に勝つための対策が求められます。
競争激化への対策の1つに、価格引き下げがあります。他社との差別化を図るために、既に価格の引き下げをしている警備会社も少なくありません。 しかし、原価率が上がれば経営をひっ迫するリスクもあります。中小規模の警備会社の場合、生き残りが難しくなる可能性もあるでしょう。
IT化・AIの普及によるテクノロジーの導入
IT技術やAIを上手く活用できれば、人の手で行われてきた業務の一部を機械に代替させることが可能です。 警備会社がテクノロジーを導入するメリットは、下記の通りです。
- 業務を効率化できる
- 人件費を削減できる
- 人材不足を解消できる
- 価格の引き下げに対応しやすくなる
- トラブル発生時に迅速に対応できる
IT化やAIの普及が進むことにより、多くの効果が期待できます。一方で、テクノロジーの導入には多額のコストが発生することも実情です。
新たな事業の展開に向けたM&Aの実施
激化する警備業界で他社に打ち勝つには、「価格の引き下げ」「テクノロジーの導入」「人手不足の解消」などが大きな課題となります。また、基本的な警備業務だけでは着実な成長は見込めないと言っても過言ではありません。 近年では、事業規模の拡大や新規事業の参入を目的とした警備会社のM&Aが注目されています。事業承継を目的とした売却や経営の継続が困難となった警備会社による売却など、M&Aに至る理由は多岐にわたります。
警備業界におけるM&A動向

警備業界のおけるM&Aには、下記の3つの形があります。
- 警備会社同士のM&A
- 異業種のM&A
- 会社売却・事業譲渡
M&Aの目的はそれぞれ異なるため、まずはどのような特徴があるのか確認しておきましょう。
ここでは、警備業界におけるM&A動向を詳しく解説します。
市場規模の拡大を目的とした「警備会社同士のM&A」
警備会社同士のM&Aでは、市場規模の拡大を目的とするケースが多く見られます。 警備会社が市場規模の拡大を目指すには、人材確保と設備投資が必要です。しかし、未経験から警備会社に就職しようと考える人は少なく、人手不足が発生しやすい傾向にあります。
新たに人材を採用したとしても、現場に投入するまでには一定の教育が必要となるためコストもかかります。設備投資も人材確保と同様に、コストがかかる点がネックです。
警備業界内でのM&Aであれば、譲渡企業から人材と設備を引き継ぐためコストを大幅に削減できます。新たな警備分野に挑戦したい警備会社にとっても、効果的なM&Aです。
シナジー効果の獲得を目的とした「異業種M&A」
異業種とのM&Aは、シナジー効果の獲得に繋がります。シナジー効果とは、各社のもつ特性が作用し合うことによって売上や利益を生み出すことです。 警備業界では、システム開発・訪問医療・不動産などの異業種とのM&Aが数多く実現しています。警備会社との親和性が高い業種も多く、ターゲットがマッチしやすくM&Aがスムーズに進みやすいことが特徴です。
既存の人材や設備を活用できるため、警備業界への新規参入を検討する企業にとっても魅力的なM&Aと言えます。
事業承継を目的とした「会社売却・事業譲渡」
警備業界のM&Aでは、事業承継を目的とするケースも珍しくありません。経営者にとって、自身が退いた後の事業をどうするかは重要な問題です。 警備会社を存続させる場合、後継者に任せるか会社売却・事業譲渡の形を選択する流れが一般的です。
会社売却は会社ごと売るのに対して、事業譲渡は事業の一部を譲渡します。会社売却は経営権を移転させますが、事業譲渡は譲渡する権利や財産が限られるため経営権は移りません。
今後も成長が期待できる警備業界の場合は、事業譲渡の方がメリットが大きいケースもあります。
【警備会社】M&Aによる「譲渡側」のメリット

自社のニーズに合致する方法でM&Aを実施できれば、経営者だけでなく従業員にとってもメリットが生まれます。警備会社のM&Aを検討している方は、どのようなメリットがあるのかチェックしておきましょう。
ここからは、警備会社のM&Aにおける譲渡側のメリットを4つ解説します。
(1)後継者不測問題を解決させられる
警備業界に関わらず、多くの業界で後継者不足が深刻化しています。後継者がおらず事業を引き継げない場合は、M&Aで事業継続を目指すのも1つの方法です。
M&Aの実施により廃業を避けることで、培ったノウハウを次世代に繋げられます。築き上げた警備会社をゼロにせずに済むのは、経営者にとって大きなメリットです。サービスを利用する顧客やともに歩んできた従業員への負担も最小限にできるでしょう。
(2)従業員の雇用を維持できる
M&Aで他の企業に事業を引き継ぐことで、譲渡側は従業員の雇用を維持できます。 警備会社を廃業する場合、従業員との雇用契約は解除されます。雇用の場を失った従業員は、新たに就職先を探さなければなりません。将来設計にも大きく影響するため、退職金の支払や就職先の斡旋、再就職の支援をといった対応が求められます。
また、後継者がいたとしても、競合他社に太刀打ちできなければいずれ廃業に陥る可能性もあります。従業員の雇用の場を守るために、自分の代でM&Aに踏み切る経営者も少なくありません。
(3)大手グループへの参入によって経営基盤を強化できる
経営基盤の強化を狙う場合は、大手グループへの参入が効果的です。大手グループの傘下に入ることで、経営の安定化が期待できます。 大手グループは、経営資源が豊富なだけでなくブランド力や信頼性も高いことが特徴です。経営基盤を整えることにより、コスト面がネックで取り組めなかった事業にも挑戦しやすくなります。
また、株式譲渡の場合は譲受側が資金繰りや保証債務などを行うため、経営者は一幹部として事業に集中できます。売却後も事業に携わりたい場合は、残留したい旨を予め条件提示しておきましょう。
(4)多額の資金(創業者利益)を手にできる
M&Aの実施により自社株式を譲渡すると、譲渡側の経営者は多額の資金を手にできます。 創業者利益は、「売却額-(資本+株式資本)」で求めます。会社の価値が高く評価されるほど売却額が高くなり、創業者利益は高額になる仕組みです。売却額は、会社の価値だけでなく経営状態なども考慮した上で決定します。
創業者利益は、リタイヤ後の生活資金や新規事業の資金などに充てられます。負債を抱えずに新生活や新規事業をスタートできるのは、大きなメリットです。
【警備会社】M&Aによる「譲受側」のメリット

警備会社のM&Aは、譲渡側だけでなく譲受側にも大きなメリットがあります。自社の将来性を考えてM&Aを検討する場合は、どのようなメリットがあるのか確認しておきましょう。
ここからは、警備会社のM&Aにおける譲受側のメリットを2つ解説します。
(1)事業規模の拡大につながる
事業規模の拡大に繋がることは、M&Aを実施する譲受側のメリットの1つです。事業規模の拡大は、売上アップやリスク分散につながります。
同業同士のM&Aであれば、ノウハウや経験を警備業務に活かせます。新たに新規顧客開拓をする手間も省けるでしょう。異業種が警備会社を買収する場合は、双方の強みを生かして、競合他社との差別化を図ることも可能です。 一から事業拡大を目指すとなれば、多額の先行投資が必要です。しかし、既に実績のある警備会社を買収することで、コストを大幅に削減できます。
(2)必要な経営資源をスムーズに確保できる
人材・設備・顧客などの経営資源をスムーズに確保できることも大きな魅力です。 警備員の採用や教育には手間とコストがかかりますが、買収が上手くいけば経験豊富で優秀な人材を引き継ぐことができます。一から警備員を育てる必要がないため、費用対効果を上げやすくなります。
また、買収先の設備やシステムも手に入るので、設備導入にかかるコストも大幅に抑えられるでしょう。人材不足やテクノロジーの導入などの課題を抱えている場合は、M&Aにより解決が目指せる可能性があります。
警備業界における主なM&A事例2選
警備業界におけるM&Aを成功させるには、実際にどのような買収が行われているのか知ることも大切です。事例を参考に、自社にとってメリットが大きいM&Aを目指しましょう。
ここでは、警備業界におけるM&A事例を2つ紹介します。
●セントラル警備保障株式会社×東亜警備保障株式会社
セントラル警備保障株式会社は、2023年4月に東亜警備保障の株式を取得して子会社化しました。セントラル警備保障株式会社は、施設警備・運搬警備・身辺警護などを展開しています。東亜警備保障株式会社は、栃木県内を中心に警備業務を展開する警備会社です。
セントラル警備保障株式会社がM&Aを実施した主な目的は、エリア拡大と収益の拡大化です。
●セコム株式会社×株式会社セノン
セコム株式会社は、2022年7月に株式会社セノンの株式を取得して子会社化しました。セコム株式会社は、セキュリティ事業や防災事業の他、保険事業などさまざまな事業を展開しています。株式会社セノンは、機械警備や空港保安警備などを行う警備会社です。
セコム株式会社は、シナジー効果の獲得と顧客への高品質なサービス提供を目指してM&Aを実施しました。
まとめ
警備会社が行う業務は、「施設警備」「雑踏・交通誘導警備」「運搬警備」「身辺警護」の4つに分類されます。警備会社・警備員数は増加傾向にあり、売上高がほぼ同水準で推移しています。
警備業界は競争激化が予測されているため、生き残るには価格の引き下げやテクノロジーの導入などの対策が必要です。企業成長や事業承継の手段として、M&Aを実施する警備会社も増えています。
警備会社のM&Aを検討している方は、専門知識を有するM&A助言会社「株式会社レコフ」に是非ご相談ください。
監修者プロフィール

株式会社レコフ リサーチ部 部長
澤田 英之(さわだ ひでゆき)
金融機関系研究所等で調査業務に従事後、政府系金融機関の融資担当を経て2005年レコフ入社。各業界におけるM&A動向の調査やこれに基づくレポート執筆などを担当。平成19年度農林水産省補助事業、食品企業財務動向調査委員、平成19年度内閣府経済社会総合研究所M&A究会 小研究会委員。著書・論文は「食品企業 飛躍の鍵 -グローバル化への挑戦-」(共著、株式会社ぎょうせい、2012年)、「データから見るIN-OUTの動向 -M&Aを通じた企業のグローバル化対応-」(証券アナリストジャーナル 2013年4月号、公益社団法人 日本証券アナリスト協会)など。
M&Aのことなら、
お気軽にご相談ください。
お電話で
お問い合わせ

営業時間 / 平日9:00〜18:00
M&Aを知る最新記事
選ばれる理由
M&Aのことなら、
お気軽にご相談ください。
お電話で
お問い合わせ

営業時間 / 平日9:00〜18:00