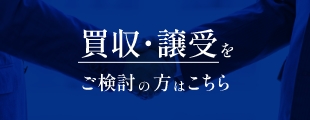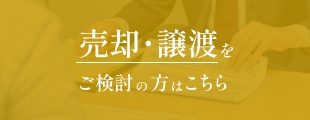平日9:00〜18:00

商社業界のM&A動向
業界別M&A
商社業界は取引の仲介だけでなく事業投資なども行う業界であり、市場規模は大きい傾向にあります。
ただし、商社業界は規模が大きい総合商社と、中小規模が多い専門商社の2種類があり、業界動向の把握は簡単ではありません。商社ではビジネスモデルの変革も進んでいて、近年は業界再編や事業拡大などを目指したM&Aが活発に行われています。
今回は、商社業界の現況とM&A動向やM&Aを行うメリットを中心に解説し、商社業界で行われた主なM&A事例も紹介します。
-
商社業界とは?定義と主なビジネスモデルについて
-
商社業界の現況・市場規模
-
商社業界の動向から見える今後の課題
-
商社業界におけるM&A動向
-
【ケース・立場別】商社業界におけるM&Aのメリット
-
商社業界における主なM&A事例5選
-
まとめ
基本合意まで無料
事業承継・譲渡売却はお気軽にご相談ください。
商社業界とは?定義と主なビジネスモデルについて

商社業界とは、輸出入貿易や商品の卸売などを事業とする「商社」で構成される業界です。
商社には、主に「総合商社」「専門商社」の2タイプが存在します。
●総合商社
総合商社は、原料・資源から加工品・サービスまで、幅広い分野の商材を取り扱う商社です。国内・国外を問わない企業間の仲介から投資や金融までを手がける総合商社は、海外にはない日本特有の業態であると言われています。
幅広い分野・事業領域を持つ総合商社は潤沢な資金力を有し、事業規模も巨大である点が特徴です。総合商社の中でも代表的な企業を指して、7大商社や5大商社と呼ぶこともあります。
●専門商社
専門商社は、鉄鋼・食品・電子機器・繊維・機械などの中で特定分野に特化し、限られた商品群で独自のノウハウ・強みを活かした事業を行う商社です。
特定分野の商材の売上比率が全体の50%以上を占めている商社が、一般的に「専門商社」と定義されています。専門商社は地域に根付いた事業活動をするケースが多く、事業規模は総合商社よりも小さいことがほとんどです。
また、商社業界の主なビジネスモデルとしては「取引仲介」「事業投資」の2種類が挙げられます。
●取引仲介(トレーディング)
取引仲介(トレーディング)は、製品・サービスを製造する企業と購入したい企業を仲介して、仲介手数料や利ざやで利益を得るビジネスモデルです。商社における本来の事業であり、専門商社は現在も取引仲介をメイン事業としています。
一方、総合商社では取引仲介の重要度が低下しており、下記の事業投資にシフトする企業が増えています。
●事業投資
事業投資は、成長が期待できる企業に投資を行い、投資先の企業価値向上などを図って利益を得るビジネスモデルです。
総合商社の事業投資は継続保有を前提としており、投資先企業の経営にも加わる点に特徴があります。
商社とメーカーの違い
商社と混同されやすいものに「メーカー」があります。
メーカーとは、原材料を仕入れて加工し、自社の製品を製造・販売する企業のことです。
対して、商社は他社が製造した製品を扱う業種であり、自社では製品を製造しない点に違いがあります。
ただし、グループの他社工場で製品を製造する商社や、顧客の要望に合う製品を調達するメーカーなど、中には明確な区別が難しいケースも存在します。
商社業界の現況・市場規模
商社業界の現況・市場規模を、「総合商社業界」「専門商社業界」に分けて解説します。
●総合商社業界
総合商社業界の市場規模(主要な企業の売上高計)の推移は、下記の通りです。
| 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|
| 約53.7兆円 | 約53.9兆円 | 約50.7兆円 | 約66.2兆円 | 約79.0兆円 |
(出典:業界動向サーチ「総合商社業界の動向や現状、ランキングなど」https://gyokai-search.com/3-syosya.htm )
2018年・2019年に横這いであった市場規模は、2020年には資源価格低迷の影響により大きく下落しました。
しかし、翌年の2021年には世界的なエネルギー需給の逼迫を受け、市場規模は大きく拡大しています。市場規模の拡大は2022年も継続している状況です。
●専門商社業界
専門商社業界の市場規模(主要な企業の売上高計)の推移は下記の通りです。
| 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
|---|---|---|---|
| 約46.5兆円 | 約47.1兆円 | 約50.3兆円 | 約53.5兆円 |
出典:業界動向サーチ「専門商社業界の動向や現状、課題などを分析」https://gyokai-search.com/3-syosya-senmon.html )
専門商社は総合商社と比べて内需依存型の傾向が強く、業界の市場規模は2018年から2021年にかけて順調に拡大を続けています。
ただし、専門商社の国内市場は飽和状態になりつつあると言われています。業界の成長が今後も同様に続くとは限らない点に注意しましょう。
商社業界の動向から見える今後の課題

商社業界は、商業全体の変化や世界情勢などの影響を受けやすい業界です。近年は特に業界を取り巻く変化が著しく起こっており、商社業界も様々な課題が発生しています。
商社業界における近年の動向から、今後の課題となるポイントを3つ抜粋して解説します。
ECサイトの普及によるトレーディング需要の減少
ECサイトの普及によって小売業者とメーカーが直接取引をするケースが増加し、商社のトレーディング需要は減少している状況です。特に取引仲介を主要事業とする専門商社には大きな影響が出ています。
ECサイトなどの技術進歩は今後も加速し、トレーディング需要の減少も続くと考えられます。したがって、商社業界は取引仲介のみに頼らないビジネスモデルへの変革が求められるでしょう。
事業投資も、もともとは取引仲介依存からの脱却を目指して確立されたビジネスモデルです。 ただし、事業投資には豊富な資金が必要であり、規模の小さい商社は事業化が難しいという課題があります。
資源価格の変動による非資源分野の事業拡大
大手総合商社は海外のエネルギー資源・金属資源に着目した事業投資を行い、資源の販売によって巨額の利益を上げてきました。
しかし、資源価格は世界情勢による価格変動が起こりやすい点が課題です。2015年の中国経済低迷による鉄価格の下落など、資源価格の変動は世界情勢の影響を強く受けています。
そのため近年は総合商社・専門商社ともに、資源分野だけでなく非資源分野にも事業を拡大する流れが進んでいます。
非資源分野とは、資源分野には含まれない事業のことです。例えば伊藤忠商事株式会社では、繊維・食料・住生活などの生活消費関連と、機械・化学品などの基礎産業関連を非資源分野としています。 ただし、資源分野も世界情勢が好況になれば、大きな収益が期待できる分野です。今後の商社業界は、資源分野・非資源分野の事業構成比のバランスを取ることが重要となるでしょう。
付加価値を目的とした「バリューチェーン」の構築
近年の商社業界は、付加価値創出を目的とした「バリューチェーン」の構築に取り組んでいます。 バリューチェーンとは、原材料調達・製造・流通・販売というサプライチェーンを、価値創造の一連の流れとして捉える考え方です。
ECサイトの普及に代表されるインターネット技術の進歩により、商社は単に商材の仲介を行うだけでは高い価値の提供が難しくなりました。商社が取引仲介事業で存在感を発揮するには、バリューチェーンの構築によって付加価値を提供することが重要です。
総合商社は国内・海外企業とのネットワーク、専門商社は特定分野への専門性という強みがあり、バリューチェーンの構築をしやすい業態と言えます。
商社業界におけるM&A動向

商社業界が直面する課題を解決する方法として、M&Aを実施するケースが増えています。 商社業界におけるM&Aにはさまざまなケースがあるため、M&Aを検討する商社はいずれのケースが自社に合うかを考えましょう。
商社業界におけるM&A動向を3つ紹介します。
事業拡大を目的としたM&A
商社は自社で製品・サービスを製造しないため、事業の現状維持よりも拡大を目指す企業が多い傾向にあります。事業拡大を目的としたM&Aは活発に行われており、大手総合商社への傘下入りを目的としたM&A(会社売却)が代表的です。
また、協業による事業拡大・事業参入を目的とした、小~中規模商社同士や異業種(商社×メーカー)とのM&A(資本業務提携)も行われています。専門商社が強みのある特定分野を拡大するために、対象分野の専門商社やメーカーと資本提携を結ぶというケースが例です。バリューチェーン構築を目的としたM&A
商社業界では総合商社を中心として、バリューチェーン構築を目的としたM&Aが進められています。商社がサプライチェーンにおける川上・川下企業の事業強化を図るために行う事業投資もM&Aの一種です。
反対に、メーカーが自社の調達・商品納入・販売を強化するために、専門商社とのM&A(株式取得)を行うケースもあります。 バリューチェーン構築を目的としたM&Aは、M&Aを実施する2社が互いのブランド力や経営資源を活用し、シナジー効果を生み出す手法です。
「事業投資→事業運営」を目的としたM&A
事業投資のM&Aでは、商社が事業投資により培ったノウハウを活かして、特定事業を買収して本格的な事業運営を行う事例も増加傾向にあります。
伊藤忠商事によるファミリーマートの買収・運営や、三菱商事とKDDIによるローソンの共同経営などが、事業運営を目的とした商社によるM&Aの好例です。 商社が事業運営を行うことによって、M&A先企業の業績改善を直接的に目指せるようになります。事業運営は非資源分野への投資でもあり、資源分野投資とのリスク分散を図れるメリットがあります。
【ケース・立場別】商社業界におけるM&Aのメリット

商社業界のM&Aを実施する際は、M&Aのメリットも理解しておきましょう。
商社業界のM&Aは「商社同士」「商社とメーカー」というケースの違いや、譲渡側・譲受側による立場の違いがあり、それぞれでM&Aのメリットは異なります。
商社業界におけるM&Aのメリットを、ケース・立場別に解説します。
【商社×商社】譲渡側(売り手)のメリット
商社同士でのM&Aにおいて、譲渡側には下記のメリットがあります。
●財務基盤の安定化や取引先拡大を図れる
専門商社はM&Aで大手総合商社の傘下になると、財務基盤が安定化します。取引仲介件数が伸ばしやすくなり、取引先拡大も図れるでしょう。
●譲受側企業の経営資源を活用して利益増大を目指せる
譲受側企業が持つ顧客ネットワークなどの経営資源を活用して、新規顧客獲得や相互送客による利益増大を目指せます。
●DX領域の強化ができる
大手総合商社はDX推進を掲げている企業が多く、M&Aにより自社のDX領域を強化できます。営業や顧客管理の効率化ができ、生産性向上につながるメリットです。
【商社×商社】譲受側(買い手)のメリット
商社同士のM&Aを実施する譲受側のメリットは、下記の3点です。
●特定分野の取引仲介を強化できる
専門商社とのM&Aを行うと、譲渡側の商社が持つ特定分野の強みを承継できます。特定分野の取引仲介を強化できる点がメリットです。
●事業拡大や海外進出を目指しやすくなる
M&Aによって既存事業の効率化・強化を行うことで、譲受側の商社は経営に余裕が生まれるようになり、事業拡大や海外進出を目指せるようになります。
●事業投資とのリスク分散ができる
資源分野への事業投資を行っている総合商社は、機械・アパレルのような非資源分野の専門商社を買収・子会社化することでリスク分散ができます。
【商社×メーカー】譲渡側(売り手)のメリット
商社とメーカーのM&Aは基本的に、特定分野の強みを伸ばすために行います。譲渡側のメリットは下記の3点です。
●特定分野で競合にはない強みを持てる
メーカーの製品を専門的に商社が仲介・販売する仕組みを作ることができ、特定分野で競合にはない強みを持てます。
●特定分野の取引仲介事業を強化できる
商社が譲渡側となる場合は、M&A先として当該分野の有力メーカーを選びます。商社は専門的な調達力・企画力を発揮でき、特定分野の取引仲介事業を強化できるでしょう。
●商社のバリューチェーン構築により、メーカーは事業強化ができる
メーカーが譲渡側となるM&Aでは、メーカーは商社が構築するバリューチェーンの恩恵を受けられます。製品の売上増加や販路拡大が期待でき、事業強化が可能です。
【商社×メーカー】譲受側(買い手)のメリット
商社とメーカーのM&Aにおいて、譲受側には下記のメリットがあります。
●自社完結のサプライチェーンにより、バリューチェーンが構築できる
商社とメーカーが提携すると、自社完結のサプライチェーンを作れます。2社の強みを付加価値としたバリューチェーンを構築できる点がメリットです。
●事業投資・事業運営ができる
商社が譲受側の場合、メーカーとのM&Aには事業投資・事業運営の性質があります。ビジネスモデルの幅を広げられ、利益の増大が可能です。
●商社のネットワークを活用し、新製品開発や海外への販路拡大を目指せる
メーカーが譲受側の場合、メーカーは商社のネットワークを活用して調達や販売をスムーズに行えるようになります。新製品開発や海外への販路拡大といった事業計画を実現しやすくなるでしょう。
商社業界における主なM&A事例5選

商社業界におけるM&Aは、商社のタイプや規模などによって違いがあります。M&Aを成功させるためには、商社が行ったM&Aの事例を参考にするのも有効です。
最後に、商社業界における主なM&A事例を5つ紹介し、具体的にどのようなM&Aが行われたかも説明します。
丸紅株式会社×株式会社ソルトン
大手総合商社の丸紅株式会社は2021年6月、電子部品の専門商社である株式会社ソルトンを完全子会社化しました。
譲渡(売り手)側 |
株式会社ソルトン |
|---|---|
譲受(買い手)側 |
丸紅株式会社 |
M&Aの目的 |
|
M&Aのスキーム |
株式譲渡 |
丸紅株式会社は2016年に電子部品事業への参入を行っており、当該事業の拡大を進めています。
需要が高まっている産業用コネクタについて、株式会社ソルトンが強みを有していることから、丸紅株式会社は株式会社ソルトンの全株式を取得し、完全子会社化しました。
株式会社GSIクレオス×桜物産株式会社
繊維・工業製品の専門商社である株式会社GSIクレオスは2022年4月、パッケージングの専門商社である桜物産株式会社を完全子会社化しました。
譲渡(売り手)側 |
桜物産株式会社 |
|---|---|
譲受(買い手)側 |
株式会社GSIクレオス |
M&Aの目的 |
|
M&Aのスキーム |
株式譲渡 |
GSIクレオスと桜物産株式会社は、各種フィルム・パッケージ製品について長年の取引を持った会社です。
2社はパッケージング分野における専門性・競争力の強化を目的として、株式会社GSIクレオスが譲受側となる株式譲渡でのM&Aを実施しています。
アルコニックス株式会社×株式会社ソーデナガノ
非鉄金属の商社・メーカーであるアルコニックス株式会社は2022年11月、金属加工メーカーの株式会社ソーデナガノを連結子会社化しました。
譲渡(売り手)側 |
株式会社ソーデナガノ |
|---|---|
譲受(買い手)側 |
アルコニックス株式会社 |
M&Aの目的 |
|
M&Aのスキーム |
株式譲渡 |
株式会社ソーデナガノはリチウムイオン電池用機構部品の特許・意匠を多く保有するメーカーです。
アルコニックス株式会社は、株式会社ソーデナガノの連結子会社化による事業へのシナジー効果と、企業価値の向上を目的としてM&Aを実施しました。
エムスリー株式会社×東和産業株式会社
幅広い医療関連事業を展開するエムスリー株式会社は2021年1月、東和産業株式会社を完全子会社化しました。
譲渡(売り手)側 |
東和産業株式会社 |
|---|---|
譲受(買い手)側 |
エムスリー株式会社 |
M&Aの目的 |
|
M&Aのスキーム |
株式譲渡 |
エムスリー株式会社は近年、医療機器業界での事業拡大を進めています。
東和産業株式会社は、関西圏に強い営業基盤を有する眼科専門商社です。エムスリー株式会社は本M&Aによってサービス提供地域の拡大ができ、医療機器・眼科領域でのDX加速を推進できるとしています。
伊藤忠商事株式会社×ほけんの窓口グループ株式会社
大手総合商社の伊藤忠商事株式会社は2019年10月、ほけんの窓口グループ株式会社を連結子会社化しました。
譲渡(売り手)側 |
ほけんの窓口グループ株式会社 |
|---|---|
譲受(買い手)側 |
伊藤忠商事株式会社 |
M&Aの目的 |
|
M&Aのスキーム |
株式譲渡 |
伊藤忠商事株式会社は2014年からほけんの窓口グループ株式会社と資本・業務提携を行っており、同社の事業成長を支援していました。
本M&Aは伊藤忠商事株式会社のネットワークやグループの強みと、ほけんの窓口グループ株式会社の強みによりシナジーを生み出すことを目的としています。
まとめ
商社業界は総合商社・専門商社の2タイプが存在し、事業内容・規模や主な課題にも違いがある業界です。
課題解決の方法としてM&Aを選択する企業は多く、事業拡大を目指すM&Aやバリューチェーン構築を目指すM&Aが実施されています。商社同士だけでなく、商社・メーカー間でのM&Aも活発です。
株式会社レコフは商社業界を含む、豊富なM&A案件の成約実績があります。商社業界のM&Aを検討している方は株式会社レコフにご相談ください。
監修者プロフィール

株式会社レコフ リサーチ部 部長
澤田 英之(さわだ ひでゆき)
金融機関系研究所等で調査業務に従事後、政府系金融機関の融資担当を経て2005年レコフ入社。各業界におけるM&A動向の調査やこれに基づくレポート執筆などを担当。平成19年度農林水産省補助事業、食品企業財務動向調査委員、平成19年度内閣府経済社会総合研究所M&A究会 小研究会委員。著書・論文は「食品企業 飛躍の鍵 -グローバル化への挑戦-」(共著、株式会社ぎょうせい、2012年)、「データから見るIN-OUTの動向 -M&Aを通じた企業のグローバル化対応-」(証券アナリストジャーナル 2013年4月号、公益社団法人 日本証券アナリスト協会)など。
M&Aのことなら、
お気軽にご相談ください。
お電話で
お問い合わせ

営業時間 / 平日9:00〜18:00
M&Aを知る最新記事
選ばれる理由
M&Aのことなら、
お気軽にご相談ください。
お電話で
お問い合わせ

営業時間 / 平日9:00〜18:00