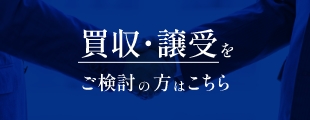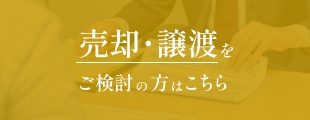平日9:00〜18:00

コンビニ業界のM&A動向
業界別M&A
近年、様々な業界で同業種や異業種とのM&Aが活発化しています。コンビニ業界でもM&Aを実行するケースが増えています。M&Aは、業界内の競争が激しくなっている中で経営維持や企業成長を目指せる手段の1つです。
コンビニ業界のM&Aを検討している方は、まずは業界の市場動向や課題を把握しておきましょう。
今回は、コンビニ業界の現状とM&Aのメリット・デメリットについて詳しく解説します。業界内のM&A事例も紹介するため、ぜひ参考にしてください。
-
コンビニエンスストア(コンビニ・CVS)業界の定義・特色
-
コンビニ業界の市場動向
-
コンビニ業界の現状と今後の課題
-
コンビニ業界におけるM&A動向
-
【コンビニ業界】M&Aによる「譲渡(売り手)側」のメリット
-
【コンビニ業界】M&Aによる「譲受(買い手)側」のメリット
-
コンビニ業界がM&Aを実行する際におさえておくべきポイント
-
コンビニ業界における主なM&A事例3選
-
まとめ
基本合意まで無料
事業承継・譲渡売却はお気軽にご相談ください。
コンビニエンスストア(コンビニ・CVS)業界の定義・特色

コンビニエンスストアとは、飲食料品小売業に分類される食品販売を中心とした小売店です。略してコンビニやCVSと呼ばれることが多く、人々の生活に欠かせない存在となっています。
経済産業省の業態分類が示すコンビニの特徴は、下記の通りです。
- 飲食料品を販売
- 売り場面積が30平方メートル以上250平方メートル未満
- 営業時間が1日で14時間以上
- セルフサービス販売
日本におけるコンビニの歴史は、1960年後半から始まっています。コンパクトな店舗に注目したスーパー各社は、コンビニ事業を開始しました。現在では、飲食料品だけでなく生活用品の販売や銀行ATMの設置など、ライフスタイルに合わせたサービス展開が拡大しています。
コンビニの主な経営形態は、次の4つです。
| フランチャイズチェーン | 本部が構築した経営ノウハウを活用して店舗運営をする |
|---|---|
| ボランタリーチェーン | 単独店が協力関係を結び連携して店舗運営をする |
| レギュラーチェーン | 各店舗が本部直営店として店舗運営をする |
| 単独店 | オーナーが開業して独自に仕入れや店舗展開をする |
コンビニの経営形態は、フランチャイズチェーンが多く見られます。
コンビニ業界の市場動向
コンビニの過去5年間における店舗数の推移は、下記の通りです。
| 店舗数 | 前年増減比 | |
|---|---|---|
| 2020年 | 55,924店 | 0.6% |
| 2021年 | 55,950店 | 0.1% |
| 2022年 | 55,838店 | ▲0.2% |
| 2023年 | 55,713店 | ▲0.2% |
| 2024年 | 55,736店 | 0.04% |
(出典:一般社団法人 日本フランチャイズチェーン協会「コンビニエンスストア統計データ-コンビニエンスストア統計時系列データ(2017年~2024年)」https://www.jfa-fc.or.jp/folder/1/img/20250120103832.pdf )
コンビニの店舗数は、2021年まで横ばい傾向が続いていたものの、2022年に減少に転じました。新型コロナウイルス感染症の拡大により、利用者の行動が大きく変化したことが一因と考えられています。
とはいえ、店舗数は55,000店以上を維持しており市場規模は保たれています。
コンビニの過去5年間における売上高の推移は、下記の通りです。
| 売上高 | 前年増減比 | |
|---|---|---|
| 2020年 | 11兆6,423億円 | ▲4.4% |
| 2021年 | 11兆7,601億円 | 1.3% |
| 2022年 | 12兆1,996億円 | 3.8% |
| 2023年 | 12兆7,321億円 | 4.4% |
| 2024年 | 12兆8,887億円 | 1.2% |
(出典:経済産業省「商業動態統計調査速報(2025年2月分)」https://www.meti.go.jp/statistics/tyo/syoudou/result/pdf/202502S.pdf )
コンビニ業界の年間売上高は、新型コロナウイルス感染症の拡大により2020年に大幅に減少しました。しかし、新型コロナウイルス感染症が終息に向かったことで、2021年以降は売上高が回復しています。
コンビニ業界は店舗数の増加により売上を伸ばしてきましたが、今後は不採算店舗を整理して既存店舗の売上アップを目指す方針に切り替える企業が増えると予測されています。
コンビニ業界では、各社がさまざまなビジネス展開を進めていることが特徴です。新ビジネスでの収益化やデリバリーサービス、ヘルスケア強化型店舗など、各社が独自の取り組みに力を入れています。
コンビニ業界の現状と今後の課題

コンビニ業界は、需要が安定しており市場規模が大きい状態を維持しています。しかし、業界ならではの課題に頭を悩ませている経営者は少なくありません。
ここでは、コンビニ業界の現状と今後の課題について解説します。
人手不足の深刻化
多くの業界で問題となっている人手不足の状況は、コンビニ業界でも深刻化しています。
コンビニ経営は24時間営業が中心となるため、夜間に対応する人材も必要です。客足の多さに関わらず一定数の人材を確保しなければならず、長時間労働や人件費の高騰などが起こりやすいと言えます。人件費がかさんで売上を圧迫するケースもめずらしくありません。
近年は、時短営業を容認する企業も増えつつあります。ただし、24時間営業には災害時の供給拠点としての役割もあることから、慎重に検討を進める企業が多く見られます。
人手不足を解消に向けて注目されているのが、在庫管理システムやRFIDタグをはじめとするIoTの活用です。商品の状態をリアルタイムで把握したり会計をサポートしたりできるため、従業員の業務負担が大幅に減ります。
事業戦略の見直しの必要性
国内のコンビニ店舗数は非常に多く、すでに頭打ちの状態です。
店舗数が多い一方で、人口は減少傾向が続いており、新規出店による企業成長を見込むのは難しいと言えます。国内のコンビニ業界においては、既存店舗の売上をいかに底上げできるかが重要です。
既存店舗の売上の底上げにつながる戦略の具体例は、下記の通りです。
- プライベートブランド商品の開発
- 独自の決済サービスの導入
- コンビニの利用率が低い顧客層へのアプローチ
売上アップを目指すには、競合との差別化がポイントになります。展開したいサービスや自社のリソースにあわせて、異業種とのM&Aも検討しましょう。
コンビニ業界におけるM&A動向

コンビニ業界では、同業同士だけでなく国境や業界の垣根を越えたM&Aも積極的に行われています。特に多く見られるのが、海外企業・異業種間・大手同士の3つのM&Aです。
以下では、コンビニ業界におけるM&A動向を詳しく解説します。
海外M&A
コンビニ業界では、将来性に注目して海外に店舗拡大を目指す動きが活発化しています。国内における既存店舗の売上の底上げに加えて、海外事業に力を入れる企業が増えていることが特徴です。
通常、海外での新規出店は税制や法制度などが異なるため、国内の新規出店よりも手間と時間がかかります。しかし、すでに経営基盤のある海外のコンビニと手を組むことで、手間と時間はもちろん、多様なリスクも大幅に削減できます。海外M&Aでは、アジア圏やアメリカなど人口や所得の増加が期待できる国々が人気です。
大手コンビニの「セブン-イレブン」を経営するセブン&アイ・ホールディングス(HD)は、海外のコンビニの合併・買収によるM&Aを積極的に進めています。
異業種によるM&A
コンビニ業界では、異業種とのM&Aも多く見られます。
スーパーやドラッグストアなど異業種とのM&Aは、顧客層の拡大や取り扱う商品の拡充などに効果的です。一見すると無関係に思われる業種であっても、経営ノウハウや商圏がシナジー効果を生み出す可能性があります。競合にはない魅力をアピールできれば、差別化にもつながるでしょう。
反対に、コンビニが異業種から買収されるケースもあります。コンビニが持つ顧客の購買データの活用や自社系列サービスへの消費者の囲い込みなど、コンビニを買収するメリットはさまざまあります。
コンビニ業界への新規参入を目指す企業にとって、M&Aはノウハウやブランド力を得られる効果的な方法です。
大手同士による水平型M&A
コンビニ業界では、大手同士による水平型M&Aが実行されるケースもあります。水平型M&Aとは、同じ業種や業態の企業が行うM&Aを意味します。
水平型M&Aを実行する主な目的は、下記の通りです。
- スケールメリットの享受
- 競争力の強化
- ブランド力の向上
- 業界の活性化
仕入れコストを大幅に削減したりブランド力を生かした経営戦略を実行したり、双方にとってメリットがあるM&Aと言えます。市場規模の拡大や業界再編の手段としても効果的です。双方が業界内の情報を熟知しており、大きな混乱を招くことなくM&Aを実行できます。
ただし、コンビニ業界はフランチャイズ経営が一般的で、経営統合後は調整に手間がかかるため頻繁に行われるものではありません。組織が複雑になれば、生産性に悪影響を与えるリスクもあります。
【コンビニ業界】M&Aによる「譲渡(売り手)側」のメリット

コンビニ業界のM&Aにおける譲渡(売り手)側のメリットは、主に4つあります。事業継続に課題を抱えている際は、M&Aを実行するのも1つの方法です。
ここでは、コンビニ業界のM&Aによって譲渡(売り手)側が得られるメリットを解説します。
(1)シナジー効果による企業成長の可能性が期待できる
同業同士の水平型M&Aに限らず、海外M&Aや異業種とのM&Aでもシナジー効果が得られる可能性があります。シナジー効果は企業成長にプラスに作用するため、譲渡(売り手)側にとって大きなメリットです。
「コンビニ×コインランドリー」なら雨の日の利用が増える、「コンビニ×ガソリンスタンド」なら給油のついでに商品購入を促せるなど、新しい顧客層の獲得ができます。
企業成長を課題とする経営者は、シナジー効果が期待できるM&A戦略を検討しましょう。
(2)大手企業のノウハウを取得しながら事業を継続させられる
経営に課題を抱えている企業は、大手の傘下に入ることで解決策を見出せる可能性が高くなります。大手企業とのM&Aは、ノウハウを取得しながら事業を継続したい方におすすめです。
大手企業は、様々なマーケティングや経営戦略で成長を続けてきた実績があります。生産性の効率化やIoTの活用など、自社の経営に大手企業のノウハウを落とし込むことで、売上アップも目指しやすくなります。
また、経営資源が豊富なため、倒産リスクを回避しやすくなることもメリットの1つです。
(3)従業員の雇用の継続・安定を図れる
従業員の雇用の継続により安定を図れることも、譲渡(売り手)側にとっては大きなメリットとなり得ます。
後継者問題に悩む経営者は、M&Aによって従業員の職場を守ることができます。後継者が決まらず廃業となれば、従業員は再就職先を探さなければなりません。取引先や顧客に悪影響を及ぼす可能性もあるでしょう。
しかし、M&Aの実行により、従業員・取引先・顧客をすべて譲受(買い手)側に引き継ぐことができます。周囲への影響を最小限にできるため、経営者の不安も軽減できます。
(4)個人保証から解放される
株式譲渡をする際、借入の連帯保証や担保提供の解除が可能です。経営者にとって個人保証から解放されることは、精神的な負担やプレッシャーからの解放につながります。
ただし、個人保証は株式譲渡によって自動的にはずれるわけではありません。個人保証の解除には手続きが必要で、手続きが完了するまではリスクを負ったままとなるため注意しましょう。
さらに、株式の売却価格が購入価格より高ければキャピタルゲインも実現できます。キャピタルゲインとは、資産の購入価格と売却価格の差額(利益)です。
【コンビニ業界】M&Aによる「譲受(買い手)側」のメリット
コンビニ業界のM&Aは、譲受(買い手)側にもいくつかのメリットがあります。M&Aを検討している方は、どのような効果を期待できるのかチェックしておきましょう。
ここからは、コンビニ業界のM&Aによって譲渡(売り手)側が得られるメリットを解説します。
(1)新たな商品・サービスの拡充や商圏の開拓につながる
コンビニ業界のM&Aによって、顧客に提供できる商品のラインナップが増えます。顧客満足度の向上につながり、売上アップも期待できるでしょう。商品やサービスの拡充は、顧客だけでなく企業側にとっても大きなメリットです。
さらに、商圏の開拓もできるため、顧客層の拡大や知名度の向上も目指せます。コンビニの商圏範囲は、徒歩10分以内に来店できる半径500m程度です。商圏の範囲内であれば、自社の商品やサービスをアピールしやすくなります。
(2)グループ形成によって規模の経済を発揮できる
M&Aによりグループ形成ができると、規模の経済を発揮できるようになります。
規模の経済とは、単位あたりのコストが下がって利益率の向上や価格競争で優位になるなどの経済効果が得られることをあらわす言葉です。市場シェアを高めたり新規参入をけん制したりする効果もあります。
ただし、規模の経済を発揮するには、多額の初期投資が必要です。大量生産と販売が上手くいけば十分なメリットを得られますが、売れなくなって在庫を抱えるようになれば規模の不経済へと一転するため注意しましょう。
コンビニ業界がM&Aを実行する際におさえておくべきポイント

コンビニ業界がM&Aを実行する際は、バイイングパワーを発揮させられるかが最も重要なポイントです。
バイイングパワーとは、強力な仕入れ力や購買力を意味します。優れた販売力がある企業は、バイイングパワーが大きく他の企業より有利な条件で取引ができます。M&Aによりバイイングパワーを発揮できれば、さらなる販売力の向上や顧客の囲い込みにもつながるでしょう。
M&Aを成功に導くために、下記のポイントも意識しましょう。
- 商品コードのルールを確認する
- 仕入れ先を選定する
- M&Aアドバイザーに相談する
M&Aを実行する際には、商品の一括管理がスムーズに行えるように商品コードのルールを確認しておくことが大切です。仕入れ先を選定しておくと、仕入れコストの削減を進めやすくなります。
M&Aの成功には、専門知識が豊富で実績のあるM&Aアドバイザーに相談するのもポイントです。コンビニ業界に詳しい専門家のサポートを受けることで、リスクをおさえつつメリットの大きいM&Aを目指せます。
コンビニ業界における主なM&A事例3選

コンビニ業界でのM&Aを成功させるには、実際にどのようなM&Aが実行されているのか知っておくことも大切です。スムーズかつ効果的にM&Aを実行するために、事例をチェックしておきましょう。
以下では、コンビニ業界におけるM&A事例を3つ紹介します。
株式会社ローソン×株式会社ポプラ
株式会社ローソンは、2020年に株式会社ポプラの吸収分割を行いました。
| 譲渡(売り手)側 | 株式会社ポプラ |
|---|---|
| 譲受(買い手)側 | 株式会社ローソン |
| M&Aの目的 |
|
| M&Aのスキーム | 吸収分割 |
ローソンは、国内を代表する大手コンビニの1つです。ポプラは、九州や中国・四国を中心にコンビニを展開しています。
ポプラが運営する店舗の一部は、複数のフランチャイズ本部と契約を結ぶメガフランチャイズ契約が実施されました。M&Aにより、効率的な店舗運営体制の整備が進められています。
株式会社ローソン×株式会社成城石井
株式会社ローソンは、2014年10月に株式会社成城石井の全株式を取得しました。
| 譲渡(売り手)側 | 株式会社成城石井 |
|---|---|
| 譲受(買い手)側 | 株式会社ローソン |
| M&Aの目的 | 小売事業における競争力の強化 |
| M&Aのスキーム | 株式譲渡 |
成城石井は、関東を中心に展開する高いブランド力のある高級スーパーです。
ローソンが持つ店舗立地やロジスティクス、成城石井が持つ事業基盤を組み合わせることで、大都市圏市場における二極化に対応する狙いがあります。
株式会社ファミリーマート×伊藤忠商事株式会社
株式会社ファミリーマートは、2020年に伊藤忠商事株式会社の完全子会社となりました。
| 譲渡(売り手)側 | 株式会社ファミリーマート |
|---|---|
| 譲受(買い手)側 | 伊藤忠商事株式会社 |
| M&Aの目的 | 新たなコンビニビジネスの確立 |
| M&Aのスキーム | TOB(公開買付け) |
ファミリーマートは、ローソンやセブン-イレブンと並ぶ大手コンビニです。伊藤忠商事は、世界でも幅広く活躍する大手総合商社です。
伊藤忠商事の完全子会社となることで、ファミリーマートは大規模な業態転換・経営改善を目指しました。伊藤忠商事は、人工知能を用いた業務効率化や顧客データの活用に取り組んでいます。
まとめ
コンビニ業界では、人手不足の深刻化や事業戦略の見直しなどの課題を抱えています。M&Aは、コンビニ業界のさまざまな課題を解決する手段の1つです。
コンビニ業界におけるM&Aでは、海外M&A・異業種によるM&A・大手同士の水平型M&Aの3つが注目されています。目的やメリット・デメリットを考慮した上で、自社にとって有意義な方法を選択することが重要です。
コンビニ業界におけるM&Aを検討している方は、まずは業界の情報に詳しく実績が豊富なM&Aアドバイザーに相談してみましょう。
監修者プロフィール

株式会社レコフ リサーチ部 部長
澤田 英之(さわだ ひでゆき)
金融機関系研究所等で調査業務に従事後、政府系金融機関の融資担当を経て2005年レコフ入社。各業界におけるM&A動向の調査やこれに基づくレポート執筆などを担当。平成19年度農林水産省補助事業、食品企業財務動向調査委員、平成19年度内閣府経済社会総合研究所M&A究会 小研究会委員。著書・論文は「食品企業 飛躍の鍵 -グローバル化への挑戦-」(共著、株式会社ぎょうせい、2012年)、「データから見るIN-OUTの動向 -M&Aを通じた企業のグローバル化対応-」(証券アナリストジャーナル 2013年4月号、公益社団法人 日本証券アナリスト協会)など。
M&Aのことなら、
お気軽にご相談ください。
お電話で
お問い合わせ

営業時間 / 平日9:00〜18:00
M&Aを知る最新記事
選ばれる理由
M&Aのことなら、
お気軽にご相談ください。
お電話で
お問い合わせ

営業時間 / 平日9:00〜18:00