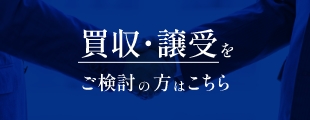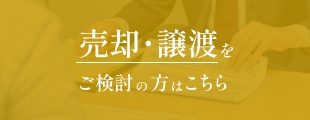平日9:00〜18:00

造船業界のM&A動向
業界別M&A
造船業界は、国内外の物流やエネルギー輸送を支える基幹産業であり、船舶の設計・建造・整備に関わる幅広い技術とノウハウが求められる分野です。大型タンカーやコンテナ船、客船など多種多様な船舶の建造において、高度な技術力と生産体制の維持が重要な役割を果たしています。
近年、日本の造船業界は、中国や韓国との競争激化に直面する中で、経営基盤の強化や事業領域の拡大を目的としたM&Aが活発化しています。これにより、企業は競争力を維持しつつ、新技術や海外市場への対応力を高めることを狙っています。
そこで今回は、日本の造船業界における歴史から市場動向・課題、さらにM&Aの最新動向や事例、成功のポイントまで詳しく解説します。造船業界に興味のある方や造船業界のM&Aを検討している方は、ぜひ参考にしてください。
-
造船業界とは?
-
日本における造船業界の歴史と市場動向
-
中国・韓国における造船業界の市場動向
-
日本の造船業界が生き残りをかけて行った主な取り組み
-
日本の造船業界が抱える主な課題
-
日本の造船業界における主なM&A最新動向
-
日本における造船業界の主なM&A事例3選
-
造船業界のM&Aを成功に導くためのポイント
-
まとめ
基本合意まで無料
事業承継・譲渡売却はお気軽にご相談ください。
造船業界とは?

造船業界とは、商船や貨物船、タンカー、客船、漁船など、さまざまな種類の船舶の設計・建造・修理・整備を手掛ける産業分野です。船舶は単なる輸送手段にとどまらず、国際物流やエネルギー供給、観光・レジャー産業にも直結しており、経済や社会の基盤を支える重要な役割を果たしています。
造船業界の最大の特徴は、広大な敷地と大型設備を必要とする点です。船舶の建造にはドックやクレーンなど特殊な施設が不可欠であり、旋盤やフライス盤といった機械加工だけでなく、職人による手作業も求められます。
建造される船舶のほとんどはオーダーメイドであり、単価が高く1つの案件で大きな利益を得られる反面、手間や時間もかかるため計画的な生産体制が求められます。
また、造船業界は扱う船舶の種類や材質、用途によって専門性が異なるため、各企業が得意分野を持つことが多い点も特色です。鉄製の大型船、アルミ製の高速船、プラスチック製の漁船など、用途や求められる強度に応じた高度な知識と技術を駆使する必要があります。
さらに、造船業界は国内外の景気変動や国際競争の影響を強く受ける産業でもあります。そのため、効率的な生産体制や技術革新、企業間連携やM&Aによる事業強化などが、競争力維持の鍵となっています。
日本における造船業界の歴史と市場動向
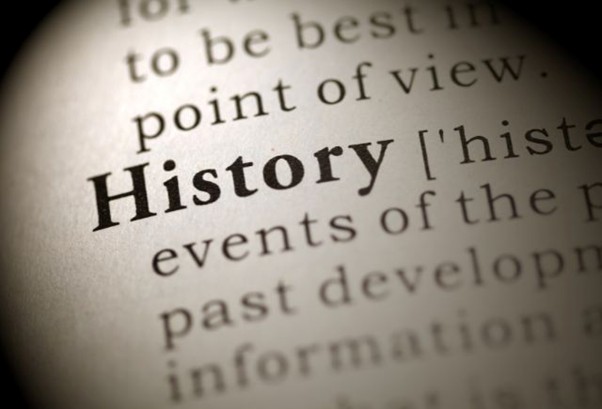
日本はユーラシア大陸の東に位置する島国であり、太平洋、日本海、東シナ海、オホーツク海と複数の海に面している海洋国です。この立地は、ユーラシア大陸の発展した文明に感化されながらも外敵の侵入を許さないという、非常に恵まれた環境でした。
しかし、1853年の黒船来航を境に、日本は「海があれば安全だ」という認識を改めなければならなくなりました。海を渡る技術を駆使してやってくる外敵に対処するため、海を防衛する軍事力の強化が必要でした。
また、海に囲まれた小さい島国である日本には、資源が少ないという弱点があります。この状況で海外諸国と渡り合うためには、輸入した資源を加工してから輸出する「交易」で生きるほかなく、これを実現するためにも海を渡れる手段をいち早く確立しなければなりません。
外敵に備えるという点や新しい時代を生き抜くという観点からも、海軍・海運を担う造船技術の発展は急務だったのです。
ここからは、日本の造船業界がどのように発展し、競争環境の変化に対応してきたのかを時代ごとに紹介します。
1950年代~:「スエズブーム」で日本の造船業界が発展
明治時代に入ると日本の産業・社会生活を支える海運業界は大きく発展し、日本の近代化に大きく貢献しました。そして、1956年に入り新造船建造量において初の世界一を達成したのです。
1956年は、エジプトがスエズ運河の国有化を宣言した年でした。スエズ運河は地中海と紅海を結ぶ人工海面水路で、アジアとヨーロッパを最短距離で行き来できる要所です。
スエズ運河国有化宣言にイスラエル・イギリス・フランスが反発したことで、スエズ運河の利権をめぐって第二次中東戦争が勃発し、一時期はスエズ運河が通れなくなりました。
スエズ運河を通れなくなるとアフリカ大陸を迂回しなければならず、物流が著しく滞るため、船舶が不足します。また、各国が備蓄用に石油の買い付けを急いだこともあり、海運需要は一気に上がりました。
この出来事は後に「スエズブーム」と呼ばれ、日本の造船業界にとっては第二次世界大戦後に迎えた絶好のチャンスとなります。1957年には通航の見通しが立ったため、わずか1年で市況は落ち着きましたが、日本の海運業界を盛り上げるには十分でした。
スエズブームを受けて日本の世界シェアは約50%まで拡大し、高度経済成長時代には「造船業は日本のお家芸」 と言われるほど目覚ましい発展を遂げ、1984年まで世界トップのシェアに君臨しました。
1980年代~:中国・韓国の台頭で劣勢に
1984年までは世界トップのシェアを誇っていたものの、以降は国外の造船会社の台頭によって次第に雲行きが怪しくなります。
1980年代からは韓国、2000年代からは中国がシェアを伸ばしはじめ、日本の造船業界はますます難しい状況に追い込まれました。また、1985年のプラザ合意により円高が進展したことも、日本の造船業界に致命的なダメージを与えた一因となっています。
2003年に世界的な海運ブームが生まれ、2008年のリーマン・ショックまでは船舶の受注量がたくさんありましたが、そのころに発注された船舶が2010~2012年にかけて竣工したことによって需給ギャップが広がり、日本の造船業界は苦しい戦いを強いられました。
2010年代~:中国・韓国と並ぶ世界的な規模にまで成長
2000年代以降、日本の造船業界は長期的な停滞と国際競争の激化に直面していました。当時は総合重工系の大手企業が中心でしたが、この時期に著しい成長を遂げたのはオーナー系の造船専業企業です。
なかでも、現在でも名を馳せる「今治造船」は当時小規模だったにもかかわらず、M&Aを積極的に実施し、事業規模を着実に拡大しました。オイルショックや円高不況といった逆風下でも戦略的に再編・統合を進め、国内シェア1位を獲得するとともに、世界的にも中国・韓国に次ぐ第4位の規模にまで成長しました。
こうした企業努力が国内シェアを押し上げたことにより、日本の造船業界は国際市場で一定の存在感を示すようになりました。
しかし、国際市場における競争環境は依然厳しい状況が続いています。中国は船舶建造量を維持しつつシェアを拡大しており、韓国も同様に高い受注量を確保しています。一方で、日本は2020年以降、建造量・受注量ともに減少傾向にあります。
2016年~2020年の日本の船舶受注量は16~21%で推移していましたが、2021年以降はコンテナ船やLNG運搬船の受注を中国・韓国が大きく獲得し、2024年には日本の受注シェアはわずか8%にまで下落しました。
(出典:経済産業省「船舶産業を取り巻く現状」
https://www.mlit.go.jp/maritime/content/001895997.pdf)
2023年には船舶建造量が増加するなど一部で回復の兆しがありましたが、2024年の推計値では再び減少傾向が見られ、日本の造船業界が直面する課題は依然として大きいと言えます。
中国・韓国が赤字受注も辞さずシェアを拡大しているのに対し、日本が持続的な競争力を維持するには、企業間の連携や技術革新による生産効率化、さらに国際協力の強化が不可欠です。業界全体として回復基調を保つためにも、国内企業が戦略的にM&Aや事業再編を進めるとともに、世界市場の動向を見据えた柔軟な対応を行うことが求められています。
中国・韓国における造船業界の市場動向

1956年からは日本がトップクラスの造船量を誇っていましたが、2000年前後には中国・韓国が世界の造船市場で急速に存在感を高めました。
韓国は1990年代後半から2000年代にかけて、政府の巨額支援と企業統合を背景に大型造船所を整備し、総合力の高い造船企業を育成しました。これにより、韓国は短期間で日本を追い抜き、世界トップの座を確立したのです。
一方、中国は経済成長に伴う国内外の物流需要の拡大を受け、造船産業を国策の柱として位置づけ、大規模造船所の建設や国営企業の育成を推進しました。政府の手厚い支援により、造船企業は赤字受注にも対応可能な体制を整え、国際市場でのシェア拡大を積極的に進めています。
両国とも、造船業はスケールメリットが重要であることを理解しており、受注量を増やすことで建造コストを下げる戦略を採用しています。特に中国は、政府支援を受けながら大型造船所を整備することで国際競争力を確保し、韓国も過剰な公的支援に対する批判を受けつつも、企業統合や効率化により競争力を維持しています。
また、世界的な船舶需要の変動も両国の戦略に影響を与えています。2003年頃の海運ブームや、2008年のリーマン・ショック後の世界的な船余りといった変化に対しても、中国・韓国の造船企業は低価格での受注を辞さず、長期的な市場シェア確保を優先する姿勢を示していました。
このように、中国・韓国の造船業界は、政府支援や企業統合、スケールメリットの活用などを通じて、国際市場での競争力を強化し続けています。今後も世界の物流需要の増加を背景に、両国の存在感は引き続き高まると考えられます。
日本の造船業界が生き残りをかけて行った主な取り組み

日本の造船業界は、中国・韓国という強力な競合に対抗するため、主に「提携戦略」「再編」「M&A」の3つの方向で生き残りを図ってきました。
ここからは、それぞれの取り組みについて詳しく紹介します。
提携戦略
世界的な造船不況の中、スケールメリットで遅れを取っている日本では、生き残りをかけて中国との連携に本腰を入れています。日本のノウハウと中国の低コスト生産を組み合わせ、政府から多額の支援を受けている韓国勢に対抗するためです。
例として、三井E&S造船は2018年10月に中国の揚子江船業集団と合弁事業を設立し、2022年には中型液化天然ガス(LNG)船の建造を開始しました。
中国国内ではエネルギーの消費がますます拡大しており、需要が広がると見込まれています。中東諸国から運ばれてくるLNGは、中国物流の大動脈である「長江」から大型タンカーで運ばれた後、さらに内陸へ輸送するためには中型船が不可欠です。そのため、中型LNG船の需要は高まると見られています。
日本側は合弁会社に船型開発技術や品質管理ノウハウの提供で参入し、中国企業と協力して船を生産しながら、売り上げ拡大を狙います。なお、中型LNG船の需要は中国だけにではなく、同様にエネルギーの消費が増えつつある東南アジアからの注文も増えてくると予想されます。
また、川崎重工業や三菱重工業も、中国との連携強化に積極的です。川崎重工業は国内のドックを減らす一方で、中国との合弁事業では新たなドックを増設しました。三菱重工は今治造船・名村造船所といった国内の造船企業と提携しており、三井E&S造船も常石造船と業務提携しています。
再編
厳しい状況の中で、大手造船会社ではリストラ・新規事業シフトなど再編の動きが活発化しています。
国内シェア2位のジャパン マリンユナイテッド(JMU)もまた、再編の末にできた企業の1つです。もともとはJFEエンジニアリングと日立造船の1部門を統合した「ユニバーサル造船」と「アイ・エイチ・アイ・マリンユナイテッド」が合併して生まれました。
また、国内のドックを削減し、新規事業の開拓を行う動きも目立ちます。例えば、三菱重工はオーナー系の造船専業企業に一部の建造を委託する方向へ舵を切っており、その代わりエンジニアリング事業への特化に注力しています。
2021年には、今治造船とJMUの共同出資によって生まれた会社がスタートしました。大規模発注を重視していく方針で、公的な支援に支えられた中国・韓国との受注競争に挑む体制を整えています。
造船事業を残しつつ発展を遂げるためには、主に受注能力の強化と新しい市場開拓、新事業への展開が必要です。新規事業においては、各造船企業が連携を取って温室効果ガスを出さない「ゼロエミッション船」の実用化に向けた開発も進められており、多くの大手造船会社が選んだ再編・新規事業シフトは功を奏していると言えるでしょう。
M&A
M&Aとは、「企業の合併(Merger)と買収(Acquisition)」を指し、事業規模の拡大や競争力強化、新規市場への参入などを目的として行われます。単なる企業の統合ではなく、経営資源や技術、人材を効率的に活用する手段として、造船業界でも重要な戦略の1つとなっています。
日本の造船業界においても、M&Aは生き残りだけでなく、事業の強化や成長につながる手段として活用されてきました。代表的な例が、前述した今治造船です。
今治造船は、2000年代以降、国内外の造船会社の買収や統合を積極的に行い、国内シェアを押し上げるとともに、世界市場でも中国・韓国に次ぐ規模へと成長しました。M&Aにより技術力や建造能力を迅速に拡充できるだけでなく、受注能力の強化や新規事業の展開も可能となり、企業全体の競争力向上に直結しています。
さらに、M&Aを通じて、今治造船は国内外の顧客基盤を広げ、多様な船型の建造にも対応できる体制を整えています。これは、単独での成長よりも迅速かつ効率的に事業ポートフォリオを拡大できることを意味します。
造船業界全体が厳しい国際競争にさらされる中で、M&Aは日本企業が持続的に競争力を維持し、かつ海外勢に対抗するための有効な手段として、今後も重要性を増していくと考えられています。
日本の造船業界が抱える主な課題

日本の造船業界は、長年にわたる企業努力や技術革新により、国際市場で一定の存在感を示すようになりました。しかし、依然として規模や資本力の面で中国・韓国の大手に劣る部分が多く、多くの課題を抱えたままであるのが実情です。
ここでは、特に深刻とされる5つの課題について解説します。
企業間連携や統合の必要性
日本は世界シェア3位を維持しているものの、規模の面でトップの中国・韓国に劣り、政府支援も限定的です。価格競争力も高くなく、低コスト・短納期が求められる国際競争では不利な状況にあります。
2018年以降、国内では企業再編や業務提携、分社化が進み、大手企業間の資本業務提携や事業承継により競争力強化が図られています。しかし、中国・韓国でも大手同士の買収・統合が進行しており、競争は今後さらに激化する見通しです。
デジタル化・自動運航技術への対応
世界的には船舶のデジタル化や自動運航技術が急速に進展しており、運航効率や安全性向上に直結しています。日本でも実証事業は開始されていますが、海外に比べると技術開発や法整備のスピードに遅れが懸念されます。
開発段階としては、まずデータ活用による運航支援、次に遠隔操作による管理、最終的には自律運航システムの実用化が想定されており、各フェーズでの遅れが国際競争力に影響する可能性があります。
官公庁船への依存と基盤強化の必要性
商船需要が低迷する中、日本の造船会社は官公庁船への依存度を高めています。しかし、国内市場だけでは建造・整備の増加が期待しにくく、海外案件の確保が不可欠です。
これまでODA(政府開発援助)以外の受注実績は乏しく、国際市場での官公庁船分野における競争力や受注基盤の強化が課題となっています。今後は、海外展開を視野に入れた戦略的取り組みも求められます。
人材の不足と技能継承の停滞
熟練技能者の高齢化と若年層の業界離れは、日本の造船業界にとって深刻な課題です。
人材不足は生産効率の低下を招くだけでなく、技能の継承にも影響します。特定技能制度を活用した外国人労働者の受け入れなどで一定の補填は進んでいますが、根本的な解決には至っておらず、長期的な人材確保や教育体制の整備が不可欠です。
鋼材価格の高騰によるコスト圧迫
2021年以降、鋼材価格の高騰が造船コストに直撃しています。加えて、資機材費や外注加工費の上昇も重なり採算悪化が深刻化しているのが実情です。船価の上昇は国際受注競争力の低下にもつながるため、単純な価格競争に依存しない体制構築が急務と言えるでしょう。
具体策としては、自動化による生産効率向上、コスト削減のための調達体制見直し、資材価格変動へのリスク管理が挙げられます。
日本の造船業界における主なM&A最新動向

造船業界が抱える規模の制約や競争力不足、人材確保の課題などを解決する手段として、M&Aは重要な役割を果たしています。単に事業を継承するだけでなく、経営基盤の強化や新市場への進出、技術力の向上にもつながる手法として、国内外で活発に行われています。
ここからは、日本の造船業界で見られる主なM&Aのパターンについて整理します。
経営基盤と競争力の強化を目的とした同業種M&A
同業種同士のM&Aは、既存の事業領域で活用できる経営資源を集約できる点が大きなメリットです。大手企業同士が統合することでスケールメリットを享受し、建造量の増加やコスト削減につなげる動きがあります。
また、中堅企業においても、技術力とコスト競争力を両立させるための再編が進められており、受注拡大や競争力強化に直結しています。こうした取り組みは、国際市場での存在感を高めるうえでも重要な戦略です。
事業領域の拡大を目的とした隣接業種・異業種M&A
隣接業種や異業種とのM&Aは、従来の造船事業にはなかった経営資源やノウハウを獲得できる点が特徴です。防衛造船や舶用エンジン、船舶部品製造など周辺分野で再編や提携が進み、新技術の開発力向上や安定的な受注基盤の確保につながっています。
隣接業種・異業種M&Aを行うことで、従来の建造事業への依存から脱却でき、多角的な収益源をもつ企業体制の構築も目指せるでしょう。
海外進出を目的としたクロスボーダーM&A
近年では、将来的な造船需要の拡大が見込まれる新興国市場への進出を狙ったクロスボーダーM&Aも増えています。
ブラジルやベトナム、ASEAN地域など、沿岸航行船や小型船需要の伸びが期待される地域で、現地の造船会社やネットワークを持つ企業と提携するケースが見られます。
クロスボーダーM&Aにより、人件費の安い海外拠点を活用した生産体制の確立や、海外顧客基盤の確保が可能となり、日本単独では困難なコスト競争力や市場シェアの拡大を目指せるでしょう。
日本における造船業界の主なM&A事例3選

造船業界のM&Aを成功させるためには、過去に行われた実際のM&A事例を参考にするのも有効です。
ここからは、今治造船株式会社・三井E&S造船株式会社・セイカダイヤエンジン株式会社による3つのM&A事例を紹介します。「どのような目的や狙いで実施されたのか」の参考にしてください。
今治造船株式会社×ジャパンマリンユナイテッド株式会社(JMU)
今治造船株式会社は、2025年6月にジャパンマリンユナイテッド株式会社(JMU)の株式を60%取得し、子会社化することを発表しました。
| 譲渡(売り手)側 | ジャパンマリンユナイテッド株式会社(JMU) |
|---|---|
| 譲受(買い手)側 | 今治造船株式会社 |
| M&Aの目的 |
|
| M&Aのスキーム | 株式譲渡 |
今治造船株式会社は、愛媛県今治市に本社を置く日本最大手の民間造船会社です。主に大型貨物船・自動車運搬船などを中心に建造しており、国内外の海運会社との強固なネットワークを築いています。
ジャパンマリンユナイテッド株式会社(JMU)は、旧ユニバーサル造船とアイ・エイチ・アイマリンユナイテッドが統合して誕生した総合造船企業で、商船・艦艇・官公庁船の設計・建造を手がけています。
今回のM&Aにより、両社の強みを融合させることで、中国・韓国の大手造船企業と対等に競争できる体制を整えるとともに、経営判断の迅速化と業界全体の競争力向上を目指しています。
常石造船株式会社×三井E&S造船株式会社
常石造船株式会社は、2025年6月に三井E&S造船株式会社の全株式を取得し、同社を完全子会社化しました。これに伴い、三井E&S造船株式会社は「常石ソリューションズ東京ベイ株式会社」へと社名を変更しています。
| 譲渡(売り手)側 | 三井E&S造船株式会社 |
|---|---|
| 譲受(買い手)側 | 常石造船株式会社 |
| M&Aの目的 |
|
| M&Aのスキーム | 株式譲渡 |
常石造船株式会社は、広島県福山市に本社を置く日本有数の民間造船会社です。世界各国に生産・修繕拠点を展開しており、商船・次世代省エネ船の開発・建造に強みをもっています。
三井E&S造船株式会社は、東京都中央区に本社を置き、LNG船や艦艇などの建造を手がけてきた老舗の造船企業です。
両社の経営資源を統合することで、国際競争が激化する中でも持続的な成長を実現することを目指しています。
セイカダイヤエンジン株式会社×株式会社田中造船
セイカダイヤエンジン株式会社は、2024年3月に株式会社田中造船の株式を取得し、同社を子会社化しました。
| 譲渡(売り手)側 | 株式会社田中造船 |
|---|---|
| 譲受(買い手)側 | セイカダイヤエンジン株式会社 |
| M&Aの目的 |
|
| M&Aのスキーム | 株式譲渡 |
セイカダイヤエンジン株式会社は、西華産業株式会社の連結子会社であり、舶用ディーゼルエンジンの設計・製造・販売を行う企業で、エンジン制御システムや補機開発など幅広い事業を展開しています。
株式会社田中造船は、主に中小型船舶の建造や修繕を行う造船会社で、地域密着型の生産体制と確かな技術力を有しています。
今回のM&Aによって、セイカダイヤエンジンは船体からエンジンまでを一貫して扱える体制を構築し、顧客ニーズに応じた柔軟な建造計画の実現・事業領域の拡大・生産効率の向上を目指しています。
造船業界のM&Aを成功に導くためのポイント

最後に、造船業界のM&Aを成功に導くためのポイントを、譲渡側・譲受側の立場別に分かりやすく紹介します。
【譲渡(売り手)側の成功ポイント】
- 譲受側との交渉までに、自社の詳細な分析を行っておく
- 従業員のモチベーション維持や離職防止を心がける
- 買収企業を見極める
譲受側との交渉に入る前には、まず自社の財務状況・技術力・生産体制などを詳細に分析しておくことが重要です。自社の強みや改善点を明確化することで、交渉を有利に進められるほか、譲渡価格の適正化にもつながります。
また、M&Aの過程では従業員の不安が高まりやすいため、経営陣は早期に情報共有を行い、モチベーション維持や離職防止に努めることが求められます。買収企業の経営理念や事業方針を見極め、自社の技術や人材を適切に活かせる相手を選定することも成功の鍵と言えるでしょう。
【譲受(買い手)側の成功ポイント】
- 買収の目的と将来的なビジョンを明確化する
- 適正価格での購入を心がける
- 適切なデューデリジェンス・PMIを実施する
買収を進める際は、まず「なぜこの企業を買収するのか」という目的と、M&A後のビジョンを明確化することが不可欠です。短期的な利益追求だけでなく、長期的な成長戦略の中でどのようなシナジーを発揮できるかを見据える必要があります。
また、適正価格での譲受を実現するためには、財務・法務・人材面を含むデューデリジェンスを徹底し、統合後のPMI(Post Merger Integration)を計画的に実施することが求められます。
さらに、譲渡側・譲受側のいずれの立場でも、各部門におけるシナジー効果を現実的に具現化することが、M&Aを成功に導く最大の要素です。
そのためには、M&Aに関する専門知識と豊富な実績を持つ専門家に相談することが欠かせません。M&Aアドバイザーは、候補先の選定や交渉支援、契約手続きのサポートなどを一貫して行い、双方にとって最適な取引の実現を後押ししてくれます。
まとめ
造船業界では、人手不足や技術継承の課題を背景に、国内外でM&Aの動きが活発化しています。大手同士の再編や海外企業との提携など、競争力強化に向けた戦略的な取り組みが進められており、今後も業界再編の動きは続くと考えられます。
M&Aを成功させるためには、譲渡側・譲受側双方が目的を明確にし、シナジー効果を最大化することが重要です。造船業界特有のノウハウを踏まえた専門的な支援を受けることで、より円滑な取引を実現できるでしょう。
M&Aに関する実績が豊富な株式会社レコフでは、最適な相手先の紹介から契約締結までを一貫してサポートしています。造船業界のM&Aを検討している企業は、ぜひお気軽にご相談ください。
監修者プロフィール

株式会社レコフ リサーチ部 部長
澤田 英之(さわだ ひでゆき)
金融機関系研究所等で調査業務に従事後、政府系金融機関の融資担当を経て2005年レコフ入社。各業界におけるM&A動向の調査やこれに基づくレポート執筆などを担当。平成19年度農林水産省補助事業、食品企業財務動向調査委員、平成19年度内閣府経済社会総合研究所M&A究会 小研究会委員。著書・論文は「食品企業 飛躍の鍵 -グローバル化への挑戦-」(共著、株式会社ぎょうせい、2012年)、「データから見るIN-OUTの動向 -M&Aを通じた企業のグローバル化対応-」(証券アナリストジャーナル 2013年4月号、公益社団法人 日本証券アナリスト協会)など。
基本合意まで無料
事業承継・譲渡売却はお気軽にご相談ください。
M&Aのことなら、
お気軽にご相談ください。
お電話で
お問い合わせ

営業時間 / 平日9:00〜18:00
M&Aを知る最新記事
選ばれる理由
M&Aのことなら、
お気軽にご相談ください。
お電話で
お問い合わせ

営業時間 / 平日9:00〜18:00