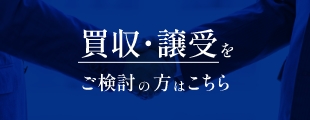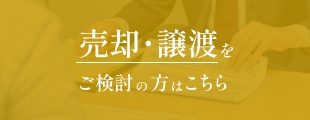平日9:00〜18:00

半導体業界のM&A動向
業界別M&A
半導体は様々な分野・製品に使用されており、半導体製造にかかわる半導体業界は大きな市場規模がある業界です。日本全体でも半導体業界は近年注目を集めている業界であり、M&Aは活発化しています。
半導体業界のM&Aを検討する際は、業界を取り巻く状況や課題、M&A動向などを把握することが重要です。
今回は半導体業界の概要から、半導体業界のM&A動向とM&Aが活発化する理由、主なM&A事例までを徹底解説します。
-
半導体業界とは
-
半導体業界の市場規模と現況
-
日本の半導体業界における今後の課題
-
半導体業界のM&A動向
-
日本の半導体業界でM&Aが盛んに行われている理由
-
【半導体業界】M&Aによる「譲渡(売り手)側」のメリット
-
【半導体業界】M&Aによる「譲受(買い手)側」のメリット
-
半導体業界における主なM&A事例3選
-
まとめ
基本合意まで無料
事業承継・譲渡売却はお気軽にご相談ください。
半導体業界とは
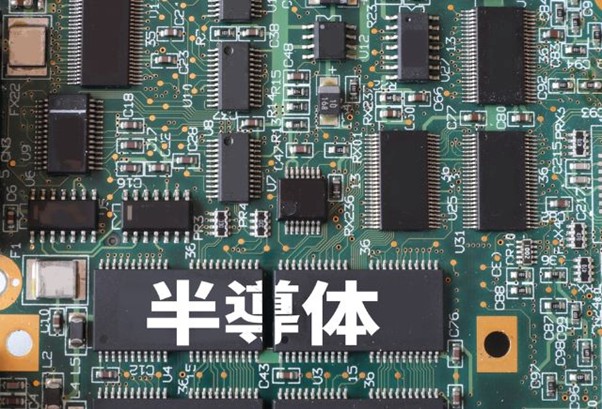
半導体業界とは、半導体の研究開発・設計・製造や販売・流通などに関わる企業で構成される業界です。
半導体業界の企業は下記の3種類に大別できます。
| 半導体メーカー | 半導体そのものを製造する企業 |
|---|---|
| 半導体製造装置メーカー | 半導体製造に必要な装置を開発する企業 |
| 半導体専門商社 | 半導体の仕入れ・販売を行う企業 |
半導体は一般的に半導体素子や集積回路のことを指し、パソコン・スマホ・自動車など多くの電気製品に組み込まれています。近年はAI設備投資やIoTによる半導体需要の拡大もあり、半導体業界は国内外の様々な企業と関係しながら事業展開をしています。
半導体業界はトレンドの変化が激しく、需要の移り変わりも大きい業界です。半導体業界の経営者は業界構造や半導体製品の需要を把握し、経営判断を行う必要があるでしょう。
半導体業界の市場規模と現況

半導体業界の市場規模は、世界的に拡大傾向にあると言えます。
下記は世界半導体市場統計から、直近5年間における世界の半導体市場規模をまとめた表です。
| 半導体市場規模 | |
| 2020年 | 約4,404億ドル |
| 2021年 | 約5,559億ドル |
| 2022年 | 約5,741億ドル |
| 2023年 | 約5,268億ドル |
| 2024年 | 約6,276億ドル |
(出典:JEITA 電子情報技術産業協会「1.WSTS 2024年秋季半導体市場予測について」https://www.jeita.or.jp/japanese/stat/wsts/docs/20241203WSTS.pdf )
(出典:米国半導体工業会(SIA:Semiconductor Industry Association)https://www.semiconductors.org/ )
2019年から2022年までは順調に成長しているものの、2023年は世界的なインフレや地政学的リスクの高まりにより、半導体需要がやや抑制気味となりましたが、2024年には過去最高を記録しており、2025年は二桁成長も予測されています。半導体業界の成長は続くと見られている状況です。
一方、日本における半導体業界の市場規模は下記の通りです。
| 半導体市場規模 | |
| 2020年 | 約365億ドル |
| 2021年 | 約437億ドル |
| 2022年 | 約482億ドル |
| 2023年 | 約468億ドル |
| 2024年 | +8.7%と予測 |
(出典:JEITA 電子情報技術産業協会「1.WSTS 2024年秋季半導体市場予測について」https://www.jeita.or.jp/japanese/stat/wsts/docs/20241203WSTS.pdf )
日本における半導体業界の市場規模は約360億~460億ドルです。予測では2024年が約509億ドル、2025年が約551億ドルであり、世界市場の1割に満たない市場規模となっています。
日本の半導体業界の市場規模は、1980年代は世界市場で5割に及ぶシェアを誇っていました。半導体業界の市場規模拡大は日本においても見られるものの、現代の日本の半導体業界は衰退している状況にあります。
日本の半導体業界が衰退している主な理由
日本の半導体業界が衰退している主な理由としては、下記の3つの要因が挙げられます。
●日米貿易摩擦
1980年代に世界市場でのシェアを握った日本産半導体は、日米貿易摩擦の原因となりました。 1986年には貿易摩擦の解消を目的として日米半導体協定が締結され、国内半導体メーカーへの貿易規制が強まります。その後、1990年代に半導体の主流がメモリ(DRAM)からロジック(CPU)へと変わっていく潮流を捉えられず、国際的な競争力を急速に失う結果となりました。
●設計と製造の水平分離の失敗
1990年代には、半導体のサプライチェーンが従来の垂直統合型から、水平分離型へと移行する変化がありました。 垂直統合型とは、半導体の設計・製造を一社で行う方式です。対して水平分離型は、設計を行うファブレス企業と、製造に特化したファウンドリ企業が連携する方式です。水平分離型は設計と製造を分業できる強みがあり、現代でも半導体業界の主流構造となっています。 一方、1990年代における日本国内の半導体メーカーは、電気・情報通信機器の親会社が競争力を失っている過程にありました。結果として半導体製造部門の切り出し・統合をスムーズに行うことができず、水平分離への移行に失敗しました。
●デジタル化の遅れ
2000年以降、パソコン・インターネット・スマホなどのデジタル機器が世界的に普及する中で、日本国内ではデジタル化が遅れました。デジタルが遅れた原因には、バブル崩壊後の景気低迷によって企業の設備投資が抑制されていたことが挙げられます。 また、政府は半導体の研究開発・技術開発に予算を注力していたものの、国内企業にこだわる自前主義に陥っていました。国際的なアライアンスの構築が遅れ、海外での製品競争力を失っています。 デジタル化の遅れによる国内デジタル市場の低迷と、海外市場での競争力低迷により、日本の半導体業界は大きく衰退する結果となりました。
(出典:経済産業省「半導体戦略(概略)」https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/joho/conference/semicon_digital/20210603008-4.pdf )
日本の半導体業界における今後の課題
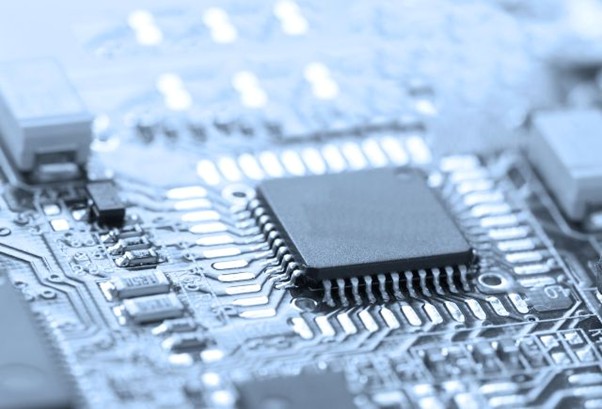
日本の半導体業界は昔と比べて衰退しているものの、近年は官民挙げて半導体産業の盛り返しを図る動きが見られています。
半導体業界に携わる方は、半導体業界の課題についても詳しく知っておくと良いでしょう。 ここからは、日本の半導体業界における今後の課題を3つ解説します。
サプライチェーンの構築
近年は半導体需要が急速に拡大しており、半導体メーカーによる供給が追いついていない状況です。半導体の供給不足を解消するためのサプライチェーン構築が課題となっています。
特に2020年第4四半期以降、世界的にファウンドリの稼働率が約95%を継続していて、生産能力の限界に達していると言われています。日本の半導体業界も、ファウンドリを中心とした生産能力の増強が必須となるでしょう。
(出典:経済産業省「半導体・デジタル産業戦略」https://www.meti.go.jp/press/2023/06/20230606003/20230606003-1.pdf )
DX化の推進
サプライチェーン構築を実現するには、半導体業界自体がDX化を推進する必要があります。DX化によって工場の自動化やデータの利活用ができるようにすることで、半導体の生産能力増強が可能となり、サプライチェーン構築にも繋がるでしょう。
DX化の推進では、新たな技術の導入やDX人材の獲得が重要です。半導体業界の企業は、製造については省人化を目指しつつ、IoT・AIやデータサイエンスを活用できる人材の確保・育成も目指さなければなりません。
人材確保
半導体業界は慢性的な人手不足に悩まされており、半導体関連産業全体では1999年~2019年の20年間で従業員数が約3割減となっています。電子情報技術産業協会によると、主要8社で今後10年間に少なくとも4万人程度の人材が追加で必要になると言われており、人材確保が大きな課題です。
(出典:経済産業省「半導体・デジタル産業戦略」https://www.meti.go.jp/press/2023/06/20230606003/20230606003-1.pdf )
特に技術者不足が深刻であるとされており、日本国内の人材はもちろん、海外人材の確保も必要な状況となっています。半導体業界は積極的な人材確保・人材育成に取り組む必要性が高いと言えるでしょう。
半導体業界のM&A動向

半導体産業の再強化を図るために政府が2021年に策定した「半導体・デジタル産業戦略」を受けて、日本の半導体業界はM&A・業界再編が活発化しつつあります。
(出典:令和6年12月23日 経済産業省「半導体・デジタル産業戦略の現状と今後」https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/joho/conference/semicon_digital/0012/handeji4r.pdf)
半導体業界のM&Aは半導体企業同士だけでなく、IT会社やファンドが半導体関連会社を買収するなど、譲渡側・譲受側の組み合わせは様々です。
半導体業界のM&A動向として、M&Aを行う業種の組み合わせや目的を紹介します。
●半導体メーカー同士のM&A
譲渡側・譲受側が共に半導体メーカーのケースでは、半導体生産技術の強化や新製品開発が主な目的です。半導体メーカー同士が提携・合併といったM&Aを実施することによって、スケールメリットを獲得しつつ、両社の強みを活かして市場競争力を伸ばせます。
また、顧客基盤の共有によって販売拡大を実現したり、製造拠点の統廃合によって経営の合理化を目指したりすることも可能です。
●譲渡側が半導体メーカー、譲受側が電子部品メーカーのM&A
譲渡側が半導体メーカー、譲受側が電子部品メーカーのケースでは、相互に成長分野での開発力強化を目的としてM&Aを実施します。
また、譲渡側の半導体メーカーにとっては大手グループの傘下に加わることで事業拡大を目指しやすくなります。譲受側の電子部品メーカーは半導体業界に参入して、事業ポートフォリオの拡充や既存製品の高性能化ができるでしょう。
●譲渡側が半導体専門商社、譲受側がIT関連商社のM&A
譲渡側が半導体専門商社、譲受側がIT関連商社のM&Aは、商社同士のM&Aであるとも言えます。相互に商材ラインナップの拡充ができ、それぞれの顧客基盤を活用した販売拡大を実現することが可能です。
また、半導体専門商社は半導体メーカーとの付き合いが深いという強みがあり、IT関連商社が半導体製品の開発事業を手がけられるメリットもあります。
日本の半導体業界でM&Aが盛んに行われている理由

半導体は各国が重要な戦略物資として捉えていて、半導体業界の競争は世界的に激化しています。 日本においても、事業拡大や生き残りを目的とした半導体企業のM&Aは活発に行われている状況です。
ここからは、日本の半導体業界でM&Aが盛んに行われている理由を3つ説明します。
半導体需要の拡大
近年は産業全体でのDX推進や、AI・IoTなどの新しい技術の登場により、半導体需要が世界的に拡大しています。総務省が公表する「令和6年 情報通信白書」によると、2023年には世界の半導体出荷額は13兆3,537億円となり、日本の半導体出荷額も大幅な増加に転じました。
(出典:総務省「令和6年版 情報通信白書|半導体市場の動向」https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r06/html/nd215400.html )
半導体需要の拡大に応えるには半導体業界が供給・流通体制を整える必要があり、生産設備の拡充や技術革新を目的としたM&Aが行われています。
半導体産業への政策支援
日本政府は半導体産業の盛り返しを図っており、半導体産業への様々な政策支援を行っています。
政策支援の例が「半導体の安定供給の確保に係る取組の認定」です。事業者が半導体の供給確保計画を策定し、経済産業大臣に認定されることで、助成金の交付を受けられます。
(出典:経済産業省「半導体」https://www.meti.go.jp/policy/economy/economic_security/semicon/index.html )
また、国内産業基盤の強靭化を目的として、海外の先端ファウンドリとの共同開発も推進しています。
(出典:経済産業省「半導体戦略(概略)」https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/joho/conference/semicon_digital/20210603008-4.pdf )
半導体産業への政策支援を利用するには、政府が推進する取り組みを実行できるだけの企業体力が必要です。 企業体力を増やすためにM&Aを検討する半導体企業が増えています。
技術革新の加速
半導体産業における技術革新が加速していることも、半導体業界でM&Aが活発化している理由の1つです。
半導体企業が新しい技術を開発・導入するには、研究開発や先端の製造装置導入などが必要です。資金力に乏しい企業は技術革新に歩調を合わせられず、凋落していくリスクがあります。
半導体企業が技術革新の加速に遅れず、自社においても技術開発を進めるために、M&Aを選択するケースがあります。
【半導体業界】M&Aによる「譲渡(売り手)側」のメリット

半導体業界のM&Aでは、譲渡側に下記のようなメリットがあります。
- 事業の成長・発展や再生を目指せる
- 大手グループの傘下に入れる
- 後継者不在の問題を解決できる
- 従業員の雇用を維持できる
- 売却益を獲得できる
自社の事業を成長させたい・販売拡大を目指したい方は、M&Aで他社と提携することで経営戦略を実現できます。
M&A先が大手グループであれば、傘下に入ることによって大手の資金力や顧客基盤を活用することが可能です。自社のみでは難しかった研究開発や設備調達もできるようになり、半導体業界における高い競争力を持てるようになります。
一方、M&Aを機に経営から退きたい方にとっては「後継者不在の問題を解決できる」「従業員の雇用を維持できる」の2点が大きなメリットとなるでしょう。
M&Aで半導体企業を譲渡すると、外部の経営者に自社の経営を任せられます。会社を廃業せずに済むため、従業員の雇用も維持することが可能です。
また、多角経営を行っている半導体企業の場合は、コア事業以外の売却によって売却益を獲得できるメリットがあります。売却益をコア事業への投資に充てることにより、事業の選択と集中を行えます。 。
【半導体業界】M&Aによる「譲受(買い手)側」のメリット
半導体企業とのM&Aを行う譲受側のメリットは、主に下記の5点です。
- 譲渡側が強みとしている技術分野を獲得できる
- 半導体事業に必要な設備を獲得できる
- 半導体関連人材を確保できる
- 事業ポートフォリオを拡充できる
- 既存事業とのシナジー効果を得られる
譲受側が半導体関連企業であれば、「技術分野を獲得できる」「半導体事業に必要な設備を獲得できる」「半導体関連人材を確保できる」が主なメリットとなるでしょう。M&Aによって他社の強みや設備・人材を獲得することにより、自社の事業拡大ができて競争力強化を実現できます。
「半導体事業に必要な設備を獲得できる」「半導体関連人材を確保できる」点は、半導体事業への新規参入などを目指す企業にとっても重要です。
半導体事業には専用設備や専門知識を持った人材が必要であり、ゼロからスタートするには多大なコストがかかります。業界外の企業が半導体事業をスピーディーに展開するには、M&Aで半導体企業を買収することが近道となるでしょう。
半導体業界における主なM&A事例3選

半導体業界におけるM&Aを成功させるためには、M&Aの事例を参考にすることも有効です。 半導体業界のM&Aは譲渡側・譲受側の組み合わせが複数あるため、自社のケースに合う事例を参考にすると良いでしょう。
ここからは、半導体業界におけるM&A事例を3つ挙げて、それぞれがどのようなM&Aを行ったかを解説します。
ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社×株式会社デンソー
株式会社デンソーは2022年2月、JASMへの出資を行うことにより半導体業界との関係性強化を行いました。
| 譲渡(売り手)側 | JASM |
|---|---|
| 譲受(買い手)側 | 株式会社デンソー |
| M&Aの目的 |
|
| M&Aのスキーム | 資本参加 |
JASMは、世界最大の半導体ファウンドリであるTSMCが日本に設立した半導体受託製造子会社で、ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社も出資しています。
株式会社デンソーは自動車部品などの開発・製造を行う企業です。 JASMへの設備投資は日本政府による強力な支援を受けており、国内生産による半導体の供給安定を目指しています。
日清紡ホールディングス×ディー・クルー・テクノロジーズ株式会社
日清紡ホールディングスは2022年2月、ディー・クルー・テクノロジーズ株式会社の全株式を取得して子会社化しました。
| 譲渡(売り手)側 | ディー・クルー・テクノロジーズ株式会社 |
|---|---|
| 譲受(買い手)側 | 日清紡ホールディングス |
| M&Aの目的 |
|
| M&Aのスキーム | 株式取得 |
日清紡ホールディングスはマイクロデバイス事業を展開しており、アナログ半導体のプロバイダーとして成長・発展を目指しています。 一方のディー・クルー・テクノロジーズ株式会社は、アナログ半導体関連の技術や先端技術の開発経験がある企業です。 日清紡ホールディングスは本M&Aにより、半導体事業の成長に欠かせない事業資源を獲得しました。
株式会社オキサイド×株式会社UJ-Crystal
株式会社オキサイドは2021年10月、株式会社UJ-Crystalとの間で株式取得による資本業務提携を行いました。
| 譲渡(売り手)側 | 株式会社オキサイド |
|---|---|
| 譲受(買い手)側 | 株式会社UJ-Crystal |
| M&Aの目的 |
|
| M&Aのスキーム | 株式取得 |
株式会社オキサイドは、単結晶材料や光デバイス・レーザ装置などの製造・販売事業を展開しています。 一方の株式会社UJ-Crystalは、溶液法を用いたパワー半導体SiC単結晶の開発・製造や販売事業を展開するスタートアップ企業です。 株式会社オキサイドは出資を通じて、パワー半導体の素材となるSiC単結晶の量産化を目指しています。
まとめ
半導体業界は世界の市場規模が拡大傾向にあり、市場の競争が激化しています。日本の半導体業界においても、サプライチェーン構築やDX化・人材確保といった課題を解決するためのM&Aが盛んに行われている状況です。
M&Aを成功させるためには、自社に合うM&A先を紹介してくれるM&Aアドバイザーを利用しましょう。
株式会社レコフは約2万社の顧客基盤があり、顧客企業の課題解決や目的達成につながるM&Aを提案できます。 半導体業界におけるM&Aを検討している方は、株式会社レコフにご相談ください。
監修者プロフィール

株式会社レコフ リサーチ部 部長
澤田 英之(さわだ ひでゆき)
金融機関系研究所等で調査業務に従事後、政府系金融機関の融資担当を経て2005年レコフ入社。各業界におけるM&A動向の調査やこれに基づくレポート執筆などを担当。平成19年度農林水産省補助事業、食品企業財務動向調査委員、平成19年度内閣府経済社会総合研究所M&A究会 小研究会委員。著書・論文は「食品企業 飛躍の鍵 -グローバル化への挑戦-」(共著、株式会社ぎょうせい、2012年)、「データから見るIN-OUTの動向 -M&Aを通じた企業のグローバル化対応-」(証券アナリストジャーナル 2013年4月号、公益社団法人 日本証券アナリスト協会)など。
基本合意まで無料
事業承継・譲渡売却はお気軽にご相談ください。
M&Aのことなら、
お気軽にご相談ください。
お電話で
お問い合わせ

営業時間 / 平日9:00〜18:00
M&Aを知る最新記事
選ばれる理由
M&Aのことなら、
お気軽にご相談ください。
お電話で
お問い合わせ

営業時間 / 平日9:00〜18:00