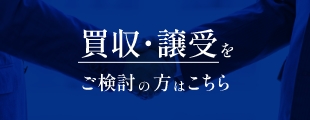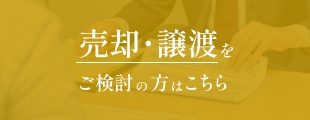平日9:00〜18:00

貿易関連業界のM&A動向
業界別M&A
貿易関連業界は経済のグローバル化に伴って市場規模が拡大しており、将来性も明るいとされている業界です。一方で人手不足や競争激化などの課題もあり、貿易関連業界ではM&Aが活発化しています。
貿易関連業界におけるM&Aを検討している方は、業界のM&A動向や事例をチェックしておくことが大切です。
そこで今回は、貿易関連業界の市場動向やM&A動向を説明した上で、M&Aの立場別のメリットと主なM&A事例、M&A実施時の注意点も解説します。
-
貿易関連業界とは?
-
貿易関連業界の市場動向|動向から分かる課題も
-
貿易関連業界のM&A動向
-
【貿易関連業界】M&Aによる「譲渡(売り手)側」のメリット
-
【貿易関連業界】M&Aによる「譲受(買い手)側」のメリット
-
貿易関連業界における主なM&A事例3選
-
貿易関連業界のM&Aを実施する際の注意点
-
まとめ
基本合意まで無料
事業承継・譲渡売却はお気軽にご相談ください。
貿易関連業界とは?

貿易関連業界とは、国際的な商取引を事業とする貿易会社を中心に構成されている業界です。国外事業者との商品の輸出入を通じて、顧客が求める商品の調達や販売を行うことが主な事業内容です。
以下では、貿易関連業界のビジネスモデルを「総合商社」「専門商社」「貿易代理店」という3つの主要なセクターに分けて、それぞれの具体的な事業内容や特徴を解説します。
(1)総合商社
総合商社とは、原材料・工業製品・エネルギー資源など幅広い商品分野において国内外の顧客と商取引を行うビジネスモデルです。総合商社は海外との貿易のために始まったという歴史があり、商社の中でも日本独自の発展を遂げた事業形態として知られています。
総合商社は取り扱う分野の広さによって数多くの顧客やパートナーとのネットワークを持っていることが特徴です。豊富な資金や情報収集能力を有していて、顧客の希望する商品を提供するだけではなく、付加価値の創出にも優れています。
また、近年は国際的なビジネスのノウハウを活用して、国内外の事業に投資するケースも増えています。
(2)専門商社
専門商社とは、特定の商品分野に特化した貿易事業を行うビジネスモデルです。幅広い商品を取り扱う総合商社に対し、売上比率が50%以上の商品がある場合は専門商社に分類されます。
専門商社は特定の商品を専門的に取り扱うため、商品を取り巻く業界や関連商品・サービスに詳しいことが特徴です。業界内でのコネクションも持っており、サプライチェーンの構築によって顧客のビジネスをサポートできる強みも持っています。
一方で、専門商社のビジネスは特定の商品分野に依存しているため、取り扱う商品が属する業界の景気に影響されやすいリスクがあります。
(3)貿易代理店
貿易代理店とは、国内外のメーカーや輸出入業者と契約して、特定の商品やブランドの取引を仲介するビジネスモデルです。買い手の紹介や価格・条件の交渉、貿易に伴うリスク対策の提案や契約締結支援などを行い、売り手が貿易によって利益を得られるようにサポートします。
貿易代理店は取引相手の国に詳しく、特殊な商習慣や法規制についても対応できることが特徴です。貿易代理店が買い手への営業活動を行ってくれるため、売り手は安心して海外の顧客との商取引を行えます。
なお、貿易代理店はあくまでも取引の仲介者であり、売主から手数料や報酬を受け取って売上とするビジネスです。取引によって生じる損益や責任は商品の売主に帰属します。
貿易関連業界の市場動向|動向から分かる課題も

貿易関連業界の市場規模は日本の輸出入額で表すことができ、基本的に拡大傾向にあります。
特に近年は自由貿易協定や経済連携協定による日本製品の需要の高まりや、円安による競争力の向上があり、輸出額は増加傾向にあります。一方で輸入額はエネルギー価格や原材料製品価格の変動による影響を受けやすく、増減を繰り返していることが特徴です。
(出典:税関 Japan Customs「対世界輸出入額及び差引額の推移」
https://www.customs.go.jp/toukei/suii/html/data/y0.pdf)
また、将来的には貿易業界全体でDX化の推進が予測されています。従来は紙ベースで行われていた書類手続きなどの業務がデジタル技術で簡易化されることにより、国際的な商取引はさらに加速すると考えられるでしょう。
しかし、貿易関連業界には多くの課題が残っており、業界で生き残るには課題解決に向けた取り組みを進める必要があります。
以下では貿易関連業界の主な課題を3つ紹介します。
課題(1)人手不足の深刻化
貿易会社ではデータ管理や書類手続きなどをアナログな手法で行うことが多く、マンパワーに頼る業務になっています。しかし少子高齢化が進む日本では多数の従業員の雇用が難しくなっており、人手不足が深刻化している状況です。
また、貿易を取り巻く環境が目まぐるしく変化していることも、人手不足につながる要因です。国ごとに異なる商習慣や規制に加え、急速に整備されている国際的なサプライチェーンにも貿易会社は対応する必要があり、人材に求める能力が高くなっています。
人手不足が深刻化している中で、業界の急速な変化にも対応できる人材を獲得することは簡単ではありません。
課題(2)競争の激化
近年の日本では多くの企業・メーカーが海外展開を進めていて、国際的な商取引の活発化に伴って貿易会社同士の競争は激化しています。
特に総合商社は幅広い商品を扱っているため、総合商社同士や専門商社との競争が発生しやすいことが特徴です。総合商社が設立する「総合商社系専門商社」や、メーカーとの関係性が強固な「メーカー系専門商社」も登場していて、商社ごとに異なる強みを打ち出しています。
また、新興国の商社がグローバル市場で存在感を強めていることも競争激化の要因です。多くの企業が新興国市場でのビジネスチャンスを模索しており、国内の商社と新興国の商社との競争が発生しています。
課題(3)為替リスクによる利益への影響
貿易関連業界では、為替リスクによる利益への影響が常に発生しています。
為替リスクとは、為替レートが変動することによる取引価格への影響のことです。特に円・ドル・ユーロといった主要通貨の為替レートの大きな変動は、貿易会社の業績悪化につながるリスクがあります。
例えば対ドルで円高が進んだ場合、輸入品の価格が安く抑えられて利益を高められる反面、輸出品の価格が海外市場で高くなって販売数低下に繋がります。
貿易会社が為替リスクによる業績への影響を少なくするために、為替予約・ヘッジ取引などの金融手法を用いることが一般的です。また、為替リスクが発生しても経営が破綻しないよう、十分な資金力を持つ必要があります。
貿易関連業界のM&A動向

貿易関連業界の課題を解決する方法としてはM&Aが有効です。人手不足や競争の激化などのあらゆる課題の解決を目指して、貿易関連業界ではM&Aが活発化しています。
以下では貿易関連業界におけるM&A動向として、異業種M&AとクロスボーダーM&Aの2つを紹介します。
事業基盤の拡大を目指した異業種M&A
貿易関連業界はさまざまな業界とのつながりがあり、事業基盤の拡大を目指すための異業種M&Aが行われています。貿易会社と異業種企業の提携により、シナジー効果を創出することが可能です。
例えば物流・運送業や卸売業とのM&Aを行えば、流通インフラの効率化や販路拡大が実現し、競合他社よりも魅力的なサービスを顧客に提案できます。製造業とのM&Aであれば、メーカー商品の国際的な取引を一手に担える強みを持てるでしょう。
また、貿易DXを促進するためにIT・テクノロジー業とM&Aを行うケースもあります。貿易に関わる手続きの自動化やデータ管理の促進ができ、人手不足の課題解消につながります。
海外市場の進出を目指したクロスボーダーM&A
貿易会社は国境をまたぐビジネスを事業としているため、海外企業との買収・合併をするクロスボーダーM&Aにも積極的です。クロスボーダーM&Aを行うことで国内同業者との競争を回避し、海外市場への進出を目指せます。
クロスボーダーM&Aは海外企業の人材を確保でき、海外の商習慣や貿易規制について強みを持てるメリットもあります。国内企業の海外進出をサポートできる商社として、業界内での優位性を発揮できるでしょう。
【貿易関連業界】M&Aによる「譲渡(売り手)側」のメリット

貿易関連業界のM&Aを進める際は、M&Aによってどのようなメリットがあるかを検討することが重要です。事業・会社を売却する譲渡(売り手)側と、買収する譲受(買い手)側とでは、M&Aによるメリットに違いがあります。
以下では、貿易関連業界のM&Aによる譲渡側のメリットを3つ紹介します。
売却益を獲得できる
譲渡側は、貿易事業や貿易会社を売却することで売却益を獲得できます。株式譲渡であれば売却益は経営者が自由に使えるお金であり、老後資金への貯蓄や、新しい事業を興すときの準備金として活用できます。
また、M&Aの条件次第では負債を譲受側に引き継いでもらうことも可能です。
特に中小の貿易会社は金融機関に個人保証を入れていることが多く、返済責任が経営者個人に及ぶリスクがあります。M&Aで負債を引き継いでもらえれば個人保証が解除されるため、返済に追われる精神的負担から解放される点もメリットです。
従業員の雇用を存続できる
貿易会社の経営が赤字の状態でも、M&Aを行えば廃業せずに済み、従業員の雇用を存続できます。
もしも貿易会社を廃業する場合は、現在雇っている従業員を解雇しなければなりません。従業員の解雇は経営者にとって精神的な負担となり、退職金の支払いが発生する場合は経済的負担も発生します。
M&Aを行って従業員の雇用を存続できれば解雇に伴う負担は発生しません。事業拡大をしている企業に買収された場合は、従業員がよりよい環境で働けるメリットもあります。
経営基盤の強化・安定化を図れる
M&Aを通じて大手商社の傘下入りをすることで、経営基盤を強化できます。大手商社の資金力を背景にデジタル技術の導入をしたり、調達ネットワークの活用によるスケールメリットを享受したりして、効率的な経営を行えるようになるでしょう。
また、貿易関連業界では多角的な事業展開を行う商社が多いものの、不採算事業を抱えているケースが少なくありません。異業種企業への事業売却を行えば事業の選択と集中ができて、経営の安定化を図れます。
【貿易関連業界】M&Aによる「譲受(買い手)側」のメリット

貿易関連業界のM&Aで譲受側が得られるメリットは、どのような譲渡企業とM&Aを進めるかによって変わります。譲受側はM&Aで達成したい目的を明確化した上で、目的達成につながるメリットがあるM&A先を選びましょう。
貿易関連業界のM&Aによる譲受側のメリットを3つ紹介します。
サプライチェーンの自社完結を実現できる
原材料・部品の輸入や製品の輸出を行う製造業にとって、貿易会社はサプライチェーンの一端を担う存在です。製造業が貿易会社を買収すればサプライチェーンの自社完結を実現できます。
サプライチェーンを自社完結する主なメリットは、第三者企業の経営リスクによる影響を受けにくくなることです。原材料などの調達を安定して行えるようになり、輸出入にかかるコストも削減できます。
M&Aによって譲受した貿易会社に優れた情報収集能力があれば、顧客ニーズや市場の変化にも素早く対応できるでしょう。
特定製品分野の強化と事業展開が期待できる
貿易会社同士のM&Aを行う場合は、専門商社や貿易代理店を買収することで特定製品分野の強化が期待できます。譲渡側の貿易会社が有しているノウハウやコネクションも引き継げるため、早期の事業展開にも繋がるでしょう。
特に貿易会社のM&Aにおいて重要な資産が、取引先や顧客情報などの無形資産です。専門商社や貿易代理店は特定製品分野に強固なネットワークを持っていて、M&Aで引き継ぐことで大手の商社にも対抗できる営業基盤を獲得できます。
海外進出・事業拡大のチャンスを得られる
国内企業が海外進出を成功させるためには、現地の法規制や商習慣に詳しい人材を獲得することが欠かせません。貿易会社は海外企業とのクロスボーダーM&Aによって必要な人材や海外拠点を得られるため、スムーズに海外進出を図れるメリットがあります。
また、クロスボーダーM&Aや異業種M&Aによって事業拡大のチャンスも得られます。海外との取引や特定製品分野の調達に強みを持てるようになり、より多くの顧客ニーズに応えることで貿易事業の強化が可能です。
貿易関連業界における主なM&A事例3選

貿易関連業界のM&Aを成功させるためには、業界のM&A事例を参考にするのも有効です。
以下で紹介する3つのM&A事例は、それぞれM&Aの目的に違いがあります。貿易関連業界のM&Aを検討する方は事例を参考に、自社におけるM&Aの目的やスキームを決定するとよいでしょう。
三洋貿易株式会社×株式会社コスモ・コンピューティングシステム
三洋貿易株式会社は2022年10月、株式会社コスモ・コンピューティングシステムの全株式を取得して子会社化しました。
| 譲渡(売り手)側 | 株式会社コスモ・コンピューティングシステム |
|---|---|
| 譲受(買い手)側 | 三洋貿易株式会社 |
| M&Aの目的 |
|
| M&Aのスキーム | 株式譲渡 |
譲受側の三洋貿易株式会社は、ゴム製品や化学品などの輸出入事業を展開する専門商社です。
一方で譲渡側の株式会社コスモ・コンピューティングシステムは、ソフトウェア受託開発や業務系システム開発などを行う企業です。
三洋貿易株式会社は本M&Aによってデジタル化に迅速に対応できる体制を構築し、競争優位性の獲得と持続的な成長によって企業価値向上が見込まれるとしています。
アサヒ衛陶株式会社×友琪貿易株式会社
アサヒ衛陶株式会社は2022年3月、友琪貿易株式会社の株式を59.2%取得して子会社化しました。
| 譲渡(売り手)側 | 友琪貿易株式会社 |
|---|---|
| 譲受(買い手)側 | アサヒ衛陶株式会社 |
| M&Aの目的 |
|
| M&Aのスキーム | 株式譲渡 |
譲受側のアサヒ衛陶株式会社は、衛生陶器製品の製造・仕入れ・販売などを行う企業です。
一方で譲渡側の友琪貿易株式会社は、古物商・輸出入・受託販売など多岐にわたる事業を展開する企業です。
アサヒ衛陶株式会社は、友琪貿易株式会社が有する古物商許可や商取引のネットワークが自社の事業展開に活用できると判断し、本M&Aを実施しました。
株式会社メニコン×板橋貿易株式会社
株式会社メニコンは2021年1月、板橋貿易株式会社の全株式を取得して子会社化しました。
| 譲渡(売り手)側 | 板橋貿易株式会社 |
|---|---|
| 譲受(買い手)側 | 株式会社メニコン |
| M&Aの目的 |
|
| M&Aのスキーム | 株式譲渡 |
譲受側の株式会社メニコンは、子会社を通じて中国でのオルソケラトロジーレンズ事業を展開している企業です。
譲渡側の板橋貿易株式会社は医療用機械器具の販売や輸出入などを事業としており、子会社として医療機器の販売会社を中国に所有しています。
株式会社メニコンは中国市場への本格進出を計画しており、板橋貿易株式会社が有する資産が事業計画に役立つとして本M&Aを実施しました。
貿易関連業界のM&Aを実施する際の注意点

貿易関連業界のM&Aを実施する際は、以下の注意点を押さえましょう。
●従業員や取引先の離反を防ぐ
貿易会社の企業価値には従業員や取引先が含まれ、M&A前に従業員の離職や取引先との契約破棄が発生すると売却益が減少します。譲渡側は企業価値を高く保つために、従業員や取引先の離反を防ぎましょう。
●通関業許可の引き継ぎができるかをチェックする
通関業許可とは、貿易会社が税関で通関手続きを行うために必要な許認可のことです。譲受側が異業種などで通関業許可を持っていない場合は、M&Aによって譲渡側の通関業許可の引き継ぎができるかをチェックしてください。
●貿易分野におけるデューデリジェンスを実施する
貿易会社には関税法への違反などによる法的リスクがあります。譲受側はM&Aによって法的リスクを承継しないよう、徹底的なデューデリジェンスの実施が必要です。
安心して貿易関連業界のM&Aを実施するためには、知識のあるM&Aアドバイザーに依頼することがおすすめです。
まとめ
貿易関連業界は市場規模が拡大しているものの、業界には人手不足や競争激化などの課題があります。課題の解決や事業拡大を目指す手段として、異業種M&AやクロスボーダーM&AなどのM&Aが活発です。
貿易関連業界のM&Aを成功させるには、立場別のメリットを理解した上で、従業員・取引先の離反防止やデューデリジェンス実施などを行う必要があります。
複雑なM&Aの手続きや交渉でつまづかないよう、知識のあるM&Aアドバイザーにも相談をしてM&Aを進めましょう。
監修者プロフィール

株式会社レコフ リサーチ部 部長
澤田 英之(さわだ ひでゆき)
金融機関系研究所等で調査業務に従事後、政府系金融機関の融資担当を経て2005年レコフ入社。各業界におけるM&A動向の調査やこれに基づくレポート執筆などを担当。平成19年度農林水産省補助事業、食品企業財務動向調査委員、平成19年度内閣府経済社会総合研究所M&A究会 小研究会委員。著書・論文は「食品企業 飛躍の鍵 -グローバル化への挑戦-」(共著、株式会社ぎょうせい、2012年)、「データから見るIN-OUTの動向 -M&Aを通じた企業のグローバル化対応-」(証券アナリストジャーナル 2013年4月号、公益社団法人 日本証券アナリスト協会)など。
基本合意まで無料
事業承継・譲渡売却はお気軽にご相談ください。
M&Aのことなら、
お気軽にご相談ください。
お電話で
お問い合わせ

営業時間 / 平日9:00〜18:00
M&Aを知る最新記事
選ばれる理由
M&Aのことなら、
お気軽にご相談ください。
お電話で
お問い合わせ

営業時間 / 平日9:00〜18:00